 |
 |
���F�_�ƂƊ�
No.34�@2003.2.1
|
�m���D�R�S
�E���ۃ��[�N�V���b�v�̊J�ÁF
�E�����P�S�N�x�_�Ɗ��������i��c�̊J��
�E���s���ƒn��������
�E�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�R�j�F�������W�{��
�E�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�S�j�F�����W�{��
�E�N�������̕��z�g��ƌi�ϐ��Ԋw
�E�u���F�_�ƂƊ��v�̃A�N�Z�X�F�P�P�P�C�P�P�P��ڂ̕��ɁI
�E�{�̏Љ�@�P�O�P�F�_�ƋZ�p��n�����l�����A�����q�F���A
�E�{�̏Љ�@�P�O�Q�F�_�ƋZ�p��n�����l���� II�A�����q�F���A
�E�����̏Љ�F
Japan-Korea Cooperative Reserach on
�E��`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o�Ɋւ���
�@
�@
���ۃ��[�N�V���b�v�̊J�ÁF
���A�W�A�̔_�Ɛ��Ԍn�ɂ����镨���z�Ɗ��e���]��
�|���ۋ��������Ɍ����ā|
�@ |
�@
�@
�@�n����̂��܂��܂ȕ����́A��C���A�����A�y�댗����ѐ�������ʂ��Ď����I�ɏz���Ă���B�������A20���I���Έȍ~�̊����Ȑl�Ԋ����́A����܂ł̎����I�ȕ����z���h�����Â��Ă���B���̌��ʁA�������ʃK�X�̑���A���s���A�y��A�����̌͊��A�L�Q���w�����̒~�ς�����l���̌����Ȃǂ��i�s���Ă���
�@
�@1992�N�ɊJ�Â��ꂽ�n���T�~�b�g�ł́A�l�ޑ����̂��߂ɒn���K�͂ł̊��ۑS�̏d�v���ɂ��Đ��E���Ɍx�����炳�ꂽ�B����ɂƂ��Ȃ��āA���݂̗J�����ׂ��ɑΏ����邽�߁A�n�����g���h�~�Ɋւ����A�̍��ۏ���A�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l��(IPCC)�A���A�C��ϓ��g�g������c(COP)���������ԂŒ�������Ă���B�܂��A�_�C�I�L�V����J�h�~�E���Ȃlj��w�����̉����Ɋւ�鍑�ۓI�Ȋ�̐ݒ�ɂ���������A������̕ۑS��ړI�Ƃ����������l�����ɂ��h�~�Ɍ��������ۓI���g�݂��A���i����Ă���B
�@
�@���A�W�A�����A�Ƃ�킯�����A�؍������ē��{�́A�_�k�n����̉������ʃK�X�̔����A����_���Y�f�Z�x�̍앨�ւ̉e���A�d������_�C�I�L�V���ɂ��y�뉘���A���������A����ѓ����E�N���������`�q�g�����앨�ɂ������X�N�ȂNj��ʂ����_�Ɗ���������Ă���B���̂悤�Ȕw�i�̒��ŁA�_�Ɗ��Z�p�������́A2001�N�Ɋ؍��_�ƐU�����_�ƉȊw�Z�p�@�A2002�N�ɒ����Ȋw�@�y��Ȋw�������Ɣ_�Ɗ����߂��鋤�ʖ����������邽�߁A3�������ɂ�錤�����͑̐��̋����Ɍ����Ċo��(MOU)����������B
�@
�@���̃��[�N�V���b�v�́A�R�������ɂ�錤�����͂̑��i�K�Ƃ��Čv�悳�ꂽ���̂ł���B�����ł́A�����A�؍��A���{�̔_�Ɗ��ɂ�����錤���҂����A�W�A�̔_�Ɛ��Ԍn�ɂ�����s�ύt�ȕ����z�̌�����Љ�����A���̊��e���̂��悢���������Ƃ߂āA���s�\�����ʓI�ȋ��������̍s���_����B
�@
| �J �� �� |
�F |
�����P�T�N�R���Q�T���i�j�`�Q�U���i�j |
�J�Ïꏊ
�@ |
�F
�@ |
�����ۉ�c��(�G�|�J������) ���z�[���Q�O�O�@
(���Ύs�|��2-20-3) |
| ��@�@�� |
�F |
�Ɨ��s���@�l �_�Ɗ��Z�p������ |
| �Q�W�͈� |
�F |
�������E�Ɨ��s���@�l���������@�ցA��w�A�s�����Ǔ� |
�@
�@
| ���@3��25��(��) |
10:00 - 10:30
�@ |
Opening and Keynote Address |
| �z�@���s(�_�Ɗ��Z�p������ ������) |
| �@ |
| Topic A: Regional Agriculture and Environment in East Asia |
| �i��F�Έ�@�N�Y(�_��) |
| �@ |
| 10:30 - 11:00 |
Impact of fertilization on environment in China |
| �@ |
���@����(�싞�y�댤����) |
| 11:00 - 11:30 |
Environmental and ecological aspects of Korean Agriculture |
| �@ |
���@��N(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
11:30 - 12:00
�@ |
Agro-Climatological backgrounds for impact assessment in East Asia |
| �@ |
�с@�z��(�_��) |
| �@ |
| ���@�H |
| �@ |
| Topic B: Greenhouse Gas Emission and Sequestration in Agro-Ecosystem |
| �i��F����@�E(�_��)�E�k�@�я�(�싞�y�댤����) |
| �@ |
13:00 - 13:25
�@ |
Greenhouse gas emissions from agricultural sources and its control |
| �@ |
�\�@�e��(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
| 13:25 - 13:50 |
Options for mitigating CH4 emissions from rice fields in China |
| �@ |
��@�c��(�싞�y�댤����) |
13:50 - 14:15
�@ |
Strategies and options for mitigating CH4 and N2O emissions from Japanese paddy fields |
| �@ |
���@��s(�_��) |
14:15 - 14:40
�@ |
Responses of agro-ecosystem to elevated atmospheric CO2 - China Rice/Wheat FACE experiment |
| �@ |
��@����(�싞�y�댤����) |
14:40 - 15:05
�@ |
Rice-FACE: a window to which the responses of agro-ecosystems to future atmosphere |
| �@ |
���с@�a�F(�_��) |
| �@ |
| �x�@�e |
| �@ |
15:20 - 15:45
�@ |
Estimating carbon sequestration in Japanese arable soils using RothC model |
| �@ |
���ˁ@�N�l(�_��) |
| �@ |
| Topic C: Cycling of Farm Chemicals in Agro-Ecosystem |
| �i��F�����@�p�F(�_��)�E���@����(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
| �@ |
| 15:45 - 16:10 |
Modeling on nitrogen cycling in rice-based agricultural system |
| �@ |
�@�E(�싞�y�댤����) |
| 16:10 - 16:35 |
Nutrient cycling in paddy soils in Taihu Lake region |
| �@ |
�k�@�я�(�싞�y�댤����) |
| �@ |
�@ |
16:35 - 17:00
�@ |
Analysis and evaluation system of water quality in a medium-sized river basin |
| �@ |
���@��(�_��) |
| �@ |
�@Reception�@�@18:00 - 20:00 |
�@
�@
| ���@3��26��(��) |
| 9:00 - 9:25 |
Transport of water and nitrate through soils in North China Plain |
| �@ |
���@����(�싞�y�댤����) |
9:25 - 9:50
�@ |
Distribution and long-term change of polycyclic aromatic hydrocarbons in Korean Soils |
| �@ |
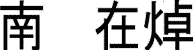 (�_�ƉȊw�Z�p�@)
(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
9:50 - 10:15
�@ |
Degradation of POPs and release kinetics of heavy metals in acid red earth of China |
| �@ |
�Ӂ@�V(�싞�y�댤����) |
| 10:15 - 10:40 |
Temporal change of dioxins in Japanese paddy field |
| �@ |
���Ɓ@�L�N(�_��) |
| �@ |
| �x�@�e |
| �@ |
10:55 - 11:20
�@ |
Development of a crop-soil database for evaluation of Cd contamination risk in relevant staple crops |
| �@ |
�����@�a�v(�_��) |
11:20 - 11:45
�@ |
Estimates and reducing techniques of methyl bromide emission from soil fumigation |
| �@ |
�����@�T�O(�_��) |
11:45 - 12:10
�@ |
Development of risk assessment methodologies for relevant pollutants in the agro-ecosystems |
| �@ |
�A�@�J��(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
| �@ |
| ���@�H |
| �@ |
| Topic D: GMO, Bio-Remediation and Bio-Diversity |
| �i��F���@�O��(�_��)�E��@�c��(�싞�y�댤����) |
| �@ |
13:10 - 13:35
�@ |
Environmental impact assessment of genetically modified crops in relation to pollen dispersion |
| �@ |
�����@�a�l�E�쓇�ΐl�E���@�O��(�_��) |
13:35 - 14:00
�@ |
Assessment of root exudates components in genetically modified crops |
| �@ |
�{�@�q��(�싞�y�댤����) |
| �@ |
�@ |
14:00 - 14:25
�@ |
In situ bioremediation of herbicide simazine-polluted soils in a golf course using degrading bacteria-enriched charcoal |
| �@ |
���@�a�L(�_��) |
14:25 - 14:50
�@ |
Assessment methods for indirect effects of introduced hymenopteran parastitoids to agro-ecosystems in Japan |
| �@ |
�]���@�~(�_��) |
| �@ |
| �x�@�e |
| �@ |
| Topic E: Construction of Environmental Resources Inventory and Its Utilization |
| �i��F���@���u(�_��)�E�A�@�J��(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
| �@ |
15:05 - 15:30
�@ |
Monitoring of environmental resources and its utilization in Korea |
| �@ |
���@����(�_�ƉȊw�Z�p�@) |
| 15:30 - 15:55 |
A 1:1,000,000 digital map and reference system of China |
| �@ |
�j�@�w��(�싞�y�댤����) |
| 15:55 - 16:20 |
Construction of soil inventory and its utilization |
| �@ |
�����@�m�E��q�@�����E�ˏ�@�a��(�_��) |
| 16:20 - 16:45 |
Construction of insect inventory and its utilization |
| �@ |
���c�@�k�i(�_��) |
| �@ |
| Discussion for Future Cooperation |
�i��F����@�G�v(�_��) |
| �@ |
| 17:20 - 17:30 |
Closing |
���@����(�싞�y�댤����) |
�@
| �@ |
�₢���킹�� |
�F |
�_�Ɗ��Z�p������ ��撲���� �������� |
| �@ |
�@ |
�@ |
��305-8604�@���Ύs�ω���3-1-3 |
| �@ |
�@ |
�@ |
Tel 029-838-8180�A Fax 029-838-8167 |
| �@ |
�@ |
�@ |
e-mail:kikaku@niaes.affrc.go.jp |
�@
�@
�����P�S�N�x�_�Ɗ��������i��c�̊J��
�@ |
�@
�@
| �@�_�Ɗ��������i��c�^�c�v�̂Ɋ�Â��A�_�ѐ��Y�ȊW�s�����ǂƊW�����@�֓�����̗v�]���A�_�Ɗ������Ɋւ���ӌ��������s���A�����̐��i��}��B�{���i��c�́A�{��c�A�������i����A�]������ō\������B |
�@
| �P�D�{ �� �c |
| ���@�� |
�F |
�����P�T�N�R���R���i���j�@�P�O���`�P�Q�� |
| ��@�� |
�F |
�_�Ɗ��Z�p���������c�� |
��@�|
�@ |
�F
�@ |
�W�s�����Njy�ъW���������@�ւ����o���ꂽ�������ɂ��Ĕ_�Ɗ��������i�̊ϓ_���猟�����A������g�ނׂ������ۑ�m�ɂ���B |
�c�@��
|
�F
|
�P�j
|
�����P�R�N�x�_�Ɗ��������i��c�ɂ����čs�����Njy�ь����@�ւ���o���ꂽ�v�]���ւ̑Ή��� |
|
�@ |
�@ |
�Q�j |
�����P�S�N�x�������i�̑��� |
|
�@ |
�@ |
�R�j |
�����P�S�N�x�]�c��� |
|
�@ |
�@ |
�S�j |
�Ɨ��s���@�l�]���ψ���ɂ�镽���P�R�N���ƔN�x�̕]�����ʕ� |
|
�@ |
�@ |
�T�j |
�����P�S�N�x�Ɏ��{����������E�V���|�W�E���̊T�v�� |
|
�@ |
�@ |
�U�j |
�����P�T�N�x�̃v���W�F�N�g�E������E�V���|�W�E�����̗\�� |
|
�@ |
�@ |
�V�j |
�s�����Njy�ь����@�ւ���̗v�] |
|
�@ |
�@ |
�W�j |
���̑� |
| �Q�W�� |
�F |
�s�����ǂ���ь����@�ւ̊W�� |
�@ |
�@ |
�_�Ɗ��Z�p�������̗������A�����A��撲�������A���������A���������A�Z���^�[���A�O���[�v���A�������Ȓ��� |
�@
| �Q�D�������i���� |
| ���@�� |
�F |
�����P�T�N�R���R���i���j�@�P�R���`�P�V�� |
| ��@�� |
�F |
�_�Ɗ��Z�p���������c�� |
��@�|
�@ |
�F
�@ |
�@CODEX�ψ���H�i�Y�����E������������iCCFAC�j�ɂ����āA�H�i���̃J�h�~�E���ő��l�Ă���������Ă���B�Q�O�O�R�N�U���ɊJ�×\���FAO/WHO�����H�i�Y�������Ɖ�iJECFA�j�ɂ����āA�䂪���Ŏ��{���Ă���u�w�������ʂɊ�Â��A�J�h�~�E���̃��X�N�]�����ēx�s���A����Ɋ�Â��Ċ�l�Ă����������Ƃ����ӂ���Ă���B��Ă���Ă���ẴJ�h�~�E���V��l�́A���Ă�0.2mg/kg�ł���B�܂��A�ʎ��A�_�C�Y�A�����A��ؓ����̔_�Y���ɑ��Ă��A���ꂼ���l�Ă���Ă���Ă���B����A�킪���ł͐H�i�q���@�Ɋ�Â��āA���Ă� 1ppm�̊�l�����肳��Ă���ɉ߂��Ȃ��B�����A�����̐V��l�Ă����F�����ƂȂ�ƁA�킪���̔_�Ƃɗ^����e���͌v��m��Ȃ��B
�@�{����ł́A��������CODEX�ψ���V��l�Č����A�u�w�I�������ʂ̉�́A�����𒆐S�ɍs���Ă���_�앨���J�h�~�E���̒ጸ���Z�p���ɂ��đ����I�Ȑ������s���B�܂��A�n��_�ƌ����Z���^�[�y�ъW�����ꏊ����A�O���[�o�������n��_�Ƃɗ^����e�����uCODEX�V����Ɍ����鍑�ۊ���l�̈��������v���ɉ�͂��A���킹�āA���̑�ɂ��Ă�����B����ɁA���̖��̉����Ɍ����ē������ǂ��x���E���͂ł��邩���c�_����B�����̘_�c��ʂ��āA�_�Ɗ��Z�p�������ƒn��̘A�g�E���͂̂������T��B
�@ |
| �c�@�� |
�F |
�u�O���[�o�������n��_�Ƃɋy�ڂ��e���Ɗ����F���̂Q�v |
�@ |
�@ |
�|�H�i���J�h�~�E���Z�x�Ɋւ���CODEX�V���
�@�@�n��_�Ƃɋy�ڂ��e���Ƃ��̑�| |
|
�@ |
�@ |
�P�j |
�������������� |
|
�@ |
�@ |
�Q�j |
CODEX�V��l�ĂƃJ�h�~�E���ጸ���Z�p |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@����G�v�i�_�Ɗ��Z�p�������@���w�������j |
|
�@ |
�@ |
�R�j |
�n��ɂ�����J�h�~�E���V��ɑ���e���]���Ƒ�Z�p |
|
�@ |
�@ |
�@ |
�@���q���i�i�_�ѐ��Y�� ���Y�ǔ_�Y�U���� �Z�p�ے��⍲�j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�\�㏹�Y�i�k�C���������_�Ǝ�����@�_�Ɗ������j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�ђ˕��j�i�H�c���_�Ǝ�����@�����j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�a�c���v�i����_�Ƒ���������@���ۑS�����j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�R�c�M���i�x�R���_�ƋZ�p�Z���^�[�@�y��엿�ے��j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�ɓ��M�v�i���挧�_�Ǝ����꒷�j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@�v�ی���i�F�{���_�ƌ����Z���^�[�@�_�Y���|���������j |
|
�@ |
�@ |
�S�j |
�A�g�E���͂̂���� |
| �Q�W�� |
�@ |
�s�����ǂ���ь����@�ւ̊W�� |
�@ |
�@ |
�_�Ɗ��Z�p�������̗������A�����A��撲�������A���������A���������A�Z���^�[���A�O���[�v���A�������Ȓ��� |
�@
| �R�D�]������ |
��@�|
�@ |
�F
�@ |
��v���ʌ�����őI�l���ꂽ��v���ʂ���A�s�����ǁA�������@�֓��̈ӌ��� |
| ���@�� |
�F |
�����P�T�N�R���S���i�j�@�X���`�P�Q�� |
| ��@�� |
�F |
�_�Ɗ��Z�p�������@���c�� |
| �c�@�� |
�F |
�P�j |
�����P�S�N�x��v���ʂ̕]���E�̑� |
|
�@ |
�@ |
�Q�j |
���̑��@ |
| �Q�W�� |
�F |
�s�����ǂ���ь����@�ւ̊W�� |
�@ |
�@ |
�_�Ɗ��Z�p�������̗������A�����A��撲�������A���������A���������A�Z���^�[���A�O���[�v���A�������Ȓ��� |
�@
�@
�@
�͂��߂�
�킪���ł͂����܂Ŏv������Ȃ������m��Ȃ����A�n���͐��s���̎���֓������B�Ƃ����̂��A���s���ɂ��H�����Y�̌����ŁA���E�l���̂P�T�����\���ȉh�{�����Ȃ��ȂǐH�����ɒ������鎖�Ԃ����ݏo����Ă��邩��ł���B
�@
����A�n����ɂ͌��݂̓��{�̐l���̂R���̂Q�ɑ�������l�������N������Ɨ\������Ă���̂ŁA���̐��s���ƐH�����Y�̒�́A�[�����𑝂�����ł���B�U���i�J�����[�x�[�X�j�̐H�����C�O�Ɉˑ����Ă���킪���́A���s���̖�肩����H���������̌�����l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�킪���ł́A�~�J�A�䕗�A���傫�Ȑ������Ƃ��ĔN�ԂP�C�V�O�O�~�����[�g���Ƃ������E���ς̂Q�{�̍~���ʂ�����̂ŁA���s���Ȃǂ͕ʂ̐��E�̂��Ƃ̂悤�ɍl���Ă��܂��B�����m���C������������o���Ă̂���N�ɂ́A���܂Ɋ�����ԂɂȂ��āA�搅�E�����𐧌����邱�Ƃ͂���B�������A���̂��Ƃ������ɐH�����Y�̑啝�ȗ������݂ɂ͂Ȃ����Ă��Ȃ��B
�@
���̂悤�ɁA���������猩�ċɂ߂Čb�܂ꂽ�H�����Y�̏�����L����ɂ�������炸�A�킪���̐H���������͂S�O���ɉ߂��Ȃ��B�U�O���ɋy�ԑ�ʂ̗A���_�Y���̐��Y�𐅎����̖ʂ��猩��ƁA���s���̖��͂킪���ɂƂ��Ă���߂đ傫���B
�@
�_�Y�����P�g�����Y����̂ɕK�v�Ȑ��̗ʂ́A�ĂłQ�C�T�O�O�g���A���ⓤ�łP�C�O�O�O�g���A���łV�C�O�O�O�g���Ƃ�����B�ƂȂ�ƁA�N�ԂR�C�O�O�O���g�����_�Y����A�����Ă���킪���́A�S�̂łT�W�O���g���̐����C�O�̂�����Ƃ���ŏ���Ă��邱�ƂɂȂ�B���̂��Ƃ����E�I�Ȑ��s���������Ă��錴���̈�ɂȂ��Ă���̂����m��Ȃ��B������p���Ɋ��Z����ƁA���W�r�㍑�ł͂P�T���l���ȏ�ɂ��Ȃ�BWorld Water Vision �u���E���r�W�����v�͎��Ԃ̐[������i���Ă���B
�@
���{������܂ō\�z���Ă������Ǘ��̋Z�p�𐢊E�ɖ𗧂Ă鎞�������B���E�̋M�d�Ȑ����g���Đ��Y�����H���������W�߂Ă��鐶�������A�^���ɔ��Ȃ��鎞�������B
�@
�l�������Ɵ��
�Q�O���I���`�Â�������́A�����ł���B���̐����̕���͐l���Ɏn�܂�B���E�̐l���͐l�ނ��o�����Ă���P�X�O�O�N�܂łɂP�U���l�ɒB�����B�l�����Q�O���l�����̂͂P�X�R�O�N�̂��Ƃł���B�P�X�U�O�N�ɂR�O���l�ɂȂ����B�S�O���l�ɂȂ����̂��P�X�V�V�N�ł���B�����āA�킸���P�Q�N��̂P�X�W�X�N�ɂ͂T�O���l�ɂȂ����B�Q�O�O�O�N�ɂ͂U�O�����A����U�R���̐l���ł���B
�@
���̐l���̑����ɂ���āA�Q�P���I�ɐ��������ꂪ���ʂ��Ă�����E�̂�����́A�����ɒW���A�X�сA�q���n�A�C�m����A�������l���A�����Ēn���̑�C�ƃI�]���w�ł���B�����ł́̕A�W�������̐��s���ƒn���������ɏœ_�Ă�B
�@
��X�̑c��́A�Ñチ�\�|�^�~�A����ȗ��A�����Ɛ��s���Ɠ����Ă����B�������A���܊g�債���鐅�s���̖��́A�V������N�I�ɂ��̐��E�����ʂ��Ă��鎑������ъ����̂Ȃ��ł��A�ł��ߏ��]������Ă����肩���m��Ȃ��B
�@
������炸���āA�l�ނ̕����j�Ɣ_�Ƃ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�_�Ƃ̍ŏ��̂��̂�����́A���L���ȓy�n�����߁A����𗘗p���A��苏�Z�\�Ȑ��Y���邽�߂̎����̕���ł�����B���\�|�^�~�A�̓��A�ҒB�́A�Z��N�O�ɐH�ƂY���邽�߂̐V�������@���������B�ނ�̓��\�|�^�~�A�̍��n����쉺���A�`�O���X��ƃ��[�t���e�X��ɂ͂��܂ꂽ������������\���݂̃C���N�암�\�ɈڏZ�����B���̐V������Z�n�́A�앨�̔���ɂ�����ɂ��D�K�n�ł��������A���n��������O�Ɋ����̂��߂ɍ앨������Ă��܂��y�n�ł������B�����̓��A�҂́A���̖��ɂ��Č��ʓI�ŒP���ȉ�������l�������B���Ȃ킿�A�a���@���ă��[�t���e�X�삩�甩�ɐ����������̂ł���B���ꂪ���_�@�̎n�܂�ł������B
�@
���̂悤�ȟ��_�@�́A����܂ł̑��̂ǂ�Ȕ_�Ɗ����������I�ɔ_�n�Ɛl�ԎЉ��ϗe�������B�����āA���͑�ʂ̗]��H���B���̂��Ƃ��A�����̊J�����x���A�V�����Љ�I���W�̊�Ղ��������Â������B�����̕������A�ߋ��Z��N�̊Ԃɏo���������ď��ł��Ă������B���̂Ȃ��ŁA��ʂ��������ɂ́A���j�I�ȋ��������ł͂Ƃ��Ă����s�����Ȃ������Ɣ_�Ƃ̕��ꂪ����B
�@
���̗��j�́A�����ɟ��_�Ƃɗ��r�����قƂ�ǂ̎Љ�A�����N���̓��ɕK�����邱�Ƃ��������ɋ����Ă���B���ɂ���Ĉ���ł͓y�n���ϗe���A�y��̗Ƃ������Ђ��₦���������������B���ɐ[���Ȃ̂����ނ̏W�ςł������B���Ƃ��A��Ɋ܂܂�鉖�ނ��y����������A�엀�x��ቺ�����A�앨�̐���E���ʂ�����ɒጸ������̂ł���B
�@
���E�̐�����
�W���ɂ́A�̐��iGreen water�j�Ɛ����iBlue water�j�Ƃ�����B�̐��̑��ʂ́A���悻�U�������R�ł���B���̗̐��\�y��ɒ~������J�ƁA����炪�A����L�@���Ɏ�荞�܂�ď��U�Ɏg������́\�́A���R���Ԍn��V���_�Ƃ̎�Ȑ��̌��ŁA���E�̐H�����Y�̂U�O���Y���Ă���B
�@
�����|�n��ɂ����ďz���Ă���n�\���ƒn�����|�́A�l�Ԃ��`���I�ɊǗ������p���Ă�����Ȑ����ł���B�����̑��ʂ́A���悻�S�������R�ł���B�l�Ԃ͂�������_�Ɨp���Ƃ��ĂQ�C�T�O�O�����R�A���̎Y�Ɨp���Ƃ��ĂV�T�O�����R�A�����p���Ƃ��ĂR�T�O�����R���g���Ă���B���̍��v�́A�S�̖̂�P�O���ɂ�����B�l�ނ��g�p���鑍�ʂR�C�W�O�O�����R�̂����̂Q�C�T�O�O�����R�͟��Ɏg���A����͂V�O���ɑ�������B���̂����̂T�T����C�ɖ߂�A�S�T���͐�����������A�͐��ѐ��w�ɖ߂�B�Q�O���I�̐��E�̐����p�̎p���\�P�Ɏ������B
�@
���ւ̈ˑ�
���j�߂Ă݂�ƁA�ߋ��ɕ��������̎Љ�����ł������悤�ɁA�ߑ�Љ�����ɂ��̊�b�������Ă���B�����A�G�W�v�g�A�C���h�A�C���h�l�V�A�A�p�L�X�^���ȂǑ����̍��X�́A�����̐H�����Y�̔����ȏ����_�n�Ɉˑ����Ă���B�����A���E�̐H�Ƃ̖�S�O���͑S�k�n�̂P�V�����߂����y�n�Ő��Y����Ă���B�C���h�A�����A�č��A�p�L�X�^���̂S�J�������E�̟��n�̔����ȏ���߁A�܂���ʂP�O�J�������E�̟��n�̂R���̂Q���߂Ă���i�\�Q�F���ʐρA��ʂQ�O�J���Ɛ��E���v�@1995�j
�@
���E�̟��p�n�̂R���̂Q���A�W�A�ɂ���B�����ł͍������Y�ʂ̖�V�O���́A���p�n�ō͔|����Ă���B�C���h�ł͂T�O���A�č��ł͂P�T���ł���B���̑��A�G�W�v�g�A�C���h�l�V�A�A�p�L�X�^�����܂ޑ����̍����A�����H�����Y�̔����ȏ����_�n�ɗ����Ă���B
�@
�����A�C���h�A�k�A�t���J�A�T�E�W�A���r�A�A�č��̒n�����̉ߏ苂�ݏグ�ʂ͍��v�łP�C�U�O�O���g������Ƃ����B�P�g���̍����Y���邽�߂ɂ͖�P�C�O�O�O�g���̐����K�v�Ȃ̂ŁA����͂P���U�C�O�O�O���g���̍����ɑ�������B����͕č��̍������Y�ʂ̔����ɂ�����B
�@
�Q�P���I���n�܂������A�_�Ƃ͈ˑR�Ƃ��ğ��Ɉˑ����Ă���B���E�̐H�Ƃ̖�S�O�����A���܂ł͟��_�n���琶�Y����Ă���B�����̔_�Ɛ��Ƃ́A����R�O�N�ԂɕK�v�ƂȂ邳��ɑ����̐H���̑啔�����A�����������_�n���狟�������ƍl���Ă���B�������A����܂ŏ����ɔ��W���Ă������u�[���́A���̂Q�O�N�ԂŒ��É����n�߂Ă���B�P�X�V�O�N����P�X�W�Q�N�܂ł́A���E�̟��ʐς͔N���ςQ���̊����ő����Ă������B�������A�P�X�W�Q�N����P�X�X�S�N�̊Ԃ́A���̊������N���ςP�D�R���ɉ��������B����Q�T�N�Ԃ̔N���ϑ������́A�ő�ł��O�D�U�����Ȃ��ł��낤�B�P�l������̟��ʐς͂P�X�V�W�N���s�[�N���������A����Ȍ�A�T�����Ȃ��Ȃ��Ă���B�Q�O�Q�O�N�ɂ́A���̃s�[�N������P�V�|�P�W����������ł��낤�B
�@
���݁A���E���̉͐삩��̈�����A�n�����炭�ݏグ�Ă��邷�ׂĂ̐��̂V�O�����A�_�Ɛ��Y�̂��߂̟��p���Ƃ��Ďg���Ă���B�Q�O�����H�Ɨp���A�P�O���������p���Ƃ��Ďg�p����Ă���B���Ɋւ���o�ϊw�͔_���ɂ͕s���ɓ����B�P�C�O�O�O�g���̐���_�Ƃŗ��p����ƂP�g���̏��������Y�ł��A����͂Q�O�O�h���ɑ������邪�A���Ȃ������H�Ɛ��Y�̂��߂Ɏg���P�S�C�O�O�O�h�����������Ƃ��ł���B���̍��͂V�O�{�ł���B���������āA�_�Ɨp���A�H�Ɨp���A�����p���̎��v�����܂��ĊȐ����߂��鋣������������ƁA�s���̂͂قƂ�Ǘ�O�Ȃ��_�ƂƂ������ƂɂȂ�ł��낤�B
�@
���̊댯��
���_�n�̑���͂܂��ɋɌ��Ƃ�����i�K�ɒB���n�߂��B���ɓK�����y�n�́A���E�̂قƂ�ǂ̒n��Ŋ��ɊJ����������ꂽ�B���p����V���ȓy�n�Ɉ����̂́A����Ŕ�p�̂�������̂ɂȂ��Ă���B���̏�A���E�̟��V�X�e���̑����́A���S�ȏ�Ԃňێ�����Ă��Ȃ��B���\�N�ɂ��킽���Ďg�p���ꂽ���V�X�e���́A�C���̕K�v���̂�����̂��S�̂�50-70%�ɒB���Ă���B�����A���̊�Ղ͉ߋ��̂ǂ̎��������@�ɂ��炳��Ă���B�����̖��_�����낵���قǂ̐����Ŗ��炩�ɂȂ����B
�@
�C���h�A�p�L�X�^���A�����A�č������Ȃǐ��E�̏d�v�ȐH�����Y�n��Œn���������ݏグ���Ă��邪�A���̂قƂ�ǂ̒n��ŁA�n�����̗��p�ʂ����R�̕⋋�ʂ������Ă���B�n���������̌����������Ƃ��������̂̓C���h�ƒ����ł���B�C���h�̑啔���̒n��ł͒n�����ʂ��ቺ���A������̑��ň�˂����オ���Ă���B�ѐ��w�̐��̌͊��ɔ����āA���p�����������A�C���h�̍������Y�ʂ͂Q�T�����������邨���ꂪ����B�����ł́A����̂قڂ��ׂĂ̏ꏊ�Œn�����ʂ��ቺ�������Ă���B�����̍����̂S�O���Y����ؖk�����ł́A�n�����ʂ��P�N�ɂP�D�U���[�g�����ቺ���Ă���B�n�����̉ߏ�g���͖ڂɌ����Ȃ����A���������[���ł���B�C���h�̎�v�ȍ��q�n�т̃p���W���u�B�ł́A�L���n��ɓn���Ēn�������N�ɂO�D�T���[�g���A�n�����[�i�B�ł͔N�ɂO�D�U����O�D�V���[�g���������Ă���B
�@
�P�X�X�V�N�Q���V���A���������̔��˂̌��ł���u��Ȃ��v���͂Ɉٕς��N�����B���ꂪ�~�܂����̂ł���B�ϓ삩��͌��܂ŁA��ꂪ���オ�����B�A���P�R�O���������B���͂͂��̂P�O�N�ɂ킽���āA���N���オ���Ă���B���オ��n��͉͓�Ȃ���͌��܂ŁA�͂邩�U�O�O�L�����[�g���ɂ���Ԃ��Ƃ������B
�@
��A�W�A�̃K���W�X��ƃC���_�X��A�A�t���J�̖k�����̃i�C����A�����A�W�A�̃A���_���A��ƃV���_���A��A�^�C�̃`���I�v������A�k�A�����J�쐼���̃R�����h��͂�������A�_���ł����~�߂�ꂽ��搅���ꂽ�肵�Ă���̂ŁA��̐����قƂ�NJC�ւ��ǂ蒅���Ȃ�����������B
�@
�^�C�̃`���I�v�����여��ł́A���̎��v�������\�ʂ����łɒ����Ă���B��̗��ʂ͑D���q�s�ɂƂ��ẮA�˂ɕs�\���ł���B�o���R�N�ł͉͐쐅���s�����Ă���̂ŁA�n�����̉ߏ苂�ݏグ�Ɉˑ��������Ă���B���̂��߃o���R�N�s�̈ꕔ���������n�߂Ă���B
�@
���s���͍���A���E�̐H�����Y�ɂƂ��čő�̋��ЂɂȂ��Ă���B�H�����Y���ǂ̂悤�ȉߒ������ǂ邩�́A���������Ƃ�������B
�@
����ɁA����܂ł̒n���K�͂̐H���\�����f���́A���̋����ʂɐ����邱�Ƃ��قƂ�ǖ������Ă���B���̌��ʁA�����̐H�Ƌ����ɂ��Ă͉ߓx�Ɋy�ϓI�ȗ\�z�����Ă���B
�@
���Ɖ��ޓy��
������엀�Ȕ��ɕς��A�͐�̗����l�Ԃ̕K�v�ɉ����ĕς��錩�Ԃ�Ƃ��āA���R�͖����̌`�Ō�������藧�Ă��J�n���Ă���B�Ȃ��ł����낵���̂́A���ɔ��������ȉ��Q�ł���B����܂ŁA�������̌Ñ�̟����I��ł������B
�@
�_�Ƃ��앨����ƁA���p���̂Ȃ��̉��ނ��y�ɂ��܂�B�ǎ��̐��ł��A�Q�O�O�|�R�O�O�������Z�x�̉��ނ��܂�ł���̂����ʂ��B�܂��A�k�n�P�w�N�^�[��������N�ԂP���g���̟��p�����g�p����͕̂W���I�Ȃ��Ƃł���B���̗ʂ̟��p�����g�p���邱�Ƃɂ���āA���̓y�n�ɂ͖��N�Q�|�T�g���̉��ނ��lj�����邱�ƂɂȂ�B���̉��ނ�����Ȃ���A���\�N�̊Ԃɂ͓r�����Ȃ��ʂ̉��ނ��W�ς���\��������B
�@
���E�̟��_�n�̂T���̂P�́A�y��ւ̉��ޏW�ςɔY�܂���Ă���B���ޏW�ς̂��߂ɁA�����A�C���h�A�p�L�X�^���A�����A�W�A�A�A�����J�̍L���n��Ŕ_�n�̐��Y�͂��ቺ���Ă���i�\�R�j�B
�@
���̖����Ƒ�
�܂��A�l���̑����ƋZ�p�̐i�����H�����Y�ɑ傫�ȉe����^���Ă���B���N��W�C�O�O�O���l���V���ɐl�ނ̒��ԓ�������Ă���B���N�A����Γ��{�l�̖�R���̂Q���a�����Ă���킯�ł���B���̂܂ܐl�������傷��A�Q�O�Q�T�N�ɕK�v�Ƃ����H�Ɛ��Y���x���ɓ��B���邽�߂ɂ́A�ő�łQ�C�O�O�O�����L�����[�g���̟��p��������ɕK�v�ł���B���̗ʂ́A�i�C����̔N�ԗ��ʂ̂Q�S�{�A�R�����h��̂P�P�O�{�ɑ�������B
�@
�ŋ߂̗\���ł́A���E�l���͂Q�O�Q�T�N�܂łɂQ�W���l�����āA�W�X���l�ɒB����Ɨ\�z����Ă���B�r�㍑���E�ł͍����I���ɐl�����Q�{�Ȃ����R�{�ɑ�������Ɨ\�z����Ă���A����܂ł��������y�[�X����������ƌ�����B
�@
�n���̎��R�V�X�e���͊g�債�Ȃ����A���E�̐l���͊g�債������B���z�ɂ���Đ��Y�����W���̗ʂ́A�������P�X�T�O�N����{�I�ɂ͕ς�Ȃ��A�Q�O�T�O�N�ɂ������炭�ς�Ȃ��ł��낤�B���̂��Ƃ͐����̎����ቺ���邾���łȂ��A�ɂ���Ă͐������̂��̂����������˂Ȃ��B
�@
���ꂩ�琔�\�N�Ԑ�ɗ\�������l����{�����Ƃ�����ɍ���ɂȂ�̂́A���E�S�̂̈�l������k�n�ʐς��������Ă��邱�Ƃł���B�Q�O���I���Έȗ��A��l�����荒��k�n�ʐς́A�O�D�Q�S�w�N�^�[������O�D�P�Q�w�N�^�[���ɔ��������B���Ƃ��A���ꂩ�甼���I�̂��������E�̍k�n���ʐς��قڈ��ɕۂ��ꂽ�Ƃ��Ă��A��l������̖ʐς͂Q�O�T�O�N�ɂ͂O�D�O�W�w�N�^�[���Ɍ������邾�낤�B
�@
���ꂩ��̐��\�N�Ԃ̐��E�̟��V�X�e���́A�N�O�D�U�����x�̊g��ɂƂǂ܂�Ɨ\�z�����B�Q�O�Q�O�N�ɂ́A���E�̈�l��������ʐς͂P�X�V�W�N�̃s�[�N�ɔ�ׁA�P�V�|�Q�W����������Ɨ\�z����Ă���B������������w�A���Ɉˑ����悤�Ƃ��Ă��鍡�A���̊�Ղ͑����̎�_�������Ă���B���Ƃ��A���ނ̏W�ρA�y���̗��o�Ƒ͐ρA�C���t���̕s���A�@���I�Η��A�\�����ʋC��ϓ��ȂǁA�Ñ�̟�����m��ʊԂɐI�܂�Ă������̂Ɠ������Ђ������������Ă���B
�@
�l�ނ̏����ɉe�����y�ڂ����铮���̒��ōł��ڂɌ����ɂ������̂̂ЂƂ��A�n�����ʂ̒ቺ�ł���B�Z���A���ޏW�ρA���H�̒��D�Ƃ��������ɔ������͐���N�O�ɑk�邪�A�n���ѐ��w�̌͊��͂����ނˉߋ������I�Ɏn�܂������ɐV�������Ȃ̂ł���B
�@
�����̟��_�Ƃ�����Â��邠����Ǝ�i�������Ⴍ�j���̂Ȃ��ŁA�n���ѐ��w�̌͊��قǏd��Ȍ��ۂ͂Ȃ��ł��낤�B�����̒n��ŁA�_�Ɗ����͑ѐ��w�Ɏ��R�ɒ��܂鐅�̗ʂ����鑬�x�Œn���������ݏグ�A�n�����ʂ𒅎��ɒቺ�����Ă���B���܂₱�̖��́A�����̒������Ɩk���A�C���h�̖k�����Ɠ암�A�p�L�X�^���̈ꕔ�n��A�č������̑啔���̒n��A����ɖk�A�t���J�A�����A�A���r�A�����Ȃǂ�����Ƃ���ŋN���Ă���B
�@
���̗��j�͘Z��N�ɋy�ԁB�ߑ���͂��悻�Q�O�O�N�̗��j�����邾���ŁA�o���̐����ɉ߂����A�܂����ʂ��o�Ă��Ȃ��̂�����ł���B�����������j����w�Ԃׂ������Ƃ��d�v�ȋ��P�Ƃ́A������ՂƂ���قƂ�ǂ̕����͐��ނ��Ă���Ƃ������Ƃł���B
�@
�_�Ɨp���̐��Y���������グ��̂ɗL���ȑ�͐���������i�\�S�j�B���Y�������P���邽�߂ɂ́A�e�n��ɓ��L�Ȕ_�k�����A�C��A�����w�I�����A�앨�I���A���g�p�����A�������A���̑��̓����ɍ������헪�����邱�Ƃł���B
�@
�ߋ������I�ɂ�����_�Ƃ��K�v�Ƃ����ő�̉ۑ�́A�y�n�̐��Y�������߂邱�ƁA�܂�P���𑝂₷���Ƃł������B�Q�P���I�Ɍ����Ă̐V�����ۑ�́A���̐��Y�������߂邱�ƁA�܂���p���P���b�g��������̎��n�ʂ𑝂₷���Ƃł��낤�B
�@
�n�����̉���
�n�������������Ă���n��Ƃ���炪���ʂ��Ă����ȋ��Ђ̗���\�T�Ɏ������B��ȋ��Ђ́A�Ɏ_���A�_��A�Ζ����w�����A���f�n�n�܁A�q�f�A�d�����A���ː������A�t�b��������щ��ނł���B
�@
�k�n���痬�o����ߏ�Ȓ��f�엿�̂ق��ɁA�ƒ{���A�Ɛ����������痈��Ɏ_�����ʂɊ܂ސ������f�̋��Ђ�����ɑ傫������B�Ƃ��ɉƒ{���A�́A���̖c��ȗʂɂ����ɕ��o�����ߏ�ȗ{���̗���ɑ傫�ȉe�����y�ڂ��Ă���B
�@
�����k���̖k���s�A�V�Îs�A�͖k�ȁA�R���Ȃł́A�����n�_�̔����ȏ�ŁA�n�����̏Ɏ_���Z�x���P���b�g��������T�O�~���O�������Ă����i���E�ی��@�\�̒�߂��������l�͂S�T�~���O�����j�B�Ɏ_���Z�x���R�O�O�~���O�����ɒB���Ă����n�_���������B���̒������s��ꂽ�̂͂P�X�X�T�N�Ȃ̂ŁA����ȍ~�A�{��ʂ̋}���ɂƂ��Ȃ��Ă����̐��l�͂���ɏ㏸�����ƍl������B�č��A�C���h�A�؍��A���{�A�C���h�l�V�A�A��p�Ȃǐ��E�̑��̒n�悩��̕����l�Ȍ��ʂ������Ă���B
�@
������
�P�w�N�^�[��������̓y�n�Łu�ǂꂾ���̐H���������邩�v�Ƃ����u�y�n�̐��Y���v���A�Q�O���I�̌㔼�̐H�����Y�̌��E�����肵���悤�ɁA�P���b�g��������̐��Łu�ǂꂾ���̐H���������邩�v�Ƃ����u���̐��Y���v���A�Q�P���I�̔_�Ɛ��Y�̌��E�����肷��B
�@
���́u���̊v���v�A�F�Ō����u�i�u���[�j�̊v���v�́A�ߋ����\�N�Ԃ́u�̊v���v�����s��������낤�B
�@
�_���A���̊Ǘ��ҁA�Љ�S�̂��x�����A���Ɏg���Ă��鐅����A�����Ƒ����̐��Y���Ɨ��v�邽�߂̕��@�͗l�X����B�܂����X�ƐV�����Z�p���o�Ă��Ă���i�\�S�j�B
�@
�������A���j�́A������ՂƂ����Љ�͂قƂ�ǖłт邱�Ƃ������Ă���B�Ȋw�I�����ƒm�������A��{�I�Ȋ��������������@�ŁA��葽���̎��n�Ƃ�荂�����Y����Nj���������ƁA�y�n�͕s�тɂȂ�A�������ՂƂ���Љ�̕���ɂȂ���ƌ������Ƃł���B�Ƃ͂����A���͂܂��܂��s���ɂȂ��Ă���B�������̐H�Ƃ̂S�O���قǂ͟��_�n�Ő��Y����Ă���B���̊����͂���ɑ����Ă䂭�ł��낤�B
�@
�T���h���E�|�X�e���́u�n���̐������L����ϗ��v�̂Ȃ��Ŏw�E����B�����Ă������ߋ��̟��Љ�̖��ƍ����̟��_�Ƃ̏Ƃ��悭���Ă��邱�ƂɁA���������B���N���Ă��鉖�ޏW�ς��琅���߂��鑈���܂ł��A�ߋ��̖��̂���Ԃ��ł���B���̂����A���݂͂܂������V�����v�f��������āA�͂���܂ł���������������ł���B
�@
�܂���P�ɁA���̕s���ȑO�������X�ƌ���Ă��Ă���B���łɑ����̓y�n�Ō��݂̐��Y�����ێ��ł��邩�ǂ������낤���Ȃ��Ă���B�����̟���Ղ̂U�O���͌��݁E��������ĂT�O�N�������Ă��Ȃ��ƌ����̂ɁA���łɑ����̓y�n�Ō��݂̐��Y�����ێ��ł��邩�ǂ����낤���Ȃ��Ă���B
�@
��Q�ɁA�y��ւ̉��ޏW�ρA�����r�ւ̓y���̗����Ƒ͐ρA��剻����s�s�ւ̟��p���̓]�p�ɂ���āA���_�n���N�H����A���p����Ղ��}���ɗ��Ă���B
�@
��R�ɁA�̊v���̋��ٓI�Ȑ������ЂƂтƂɉߑ�Ȏ��M��������A���̐�ɂ�����̋K�͂������Ȃ����Ă���B
�@
��S�ɁA�l���ƒn���̒W���ʂ̃o�����X���}���ɕ���Ă��Ă��邽�߂ɁA�������̖ڑO�ɂ�����͐l�ގj��ɂȂ������K�͂ɂȂ��Ă���B���܂���Q�T�N�̊ԂɁA���s���ɔY�ލ��̐l���͂U�{�ȏ�ɑ����A���݂̂S���V�O�O�O���l����R�O���l�ɂȂ�Ɨ\������Ă���B
�@
�Ō�ɔF�����Ă����ׂ����Ƃ́A�Q�P���I�ɗ\�z����Ă���C��ω����A�H�ƂƐ��̖��ɑS���V�������ʂ������Ă��邱�Ƃł���B��Z�_�k�������n�܂��Ĉȗ��A���܂������Ă���قǂ̋K�͂Œn���̋C�����ω��������Ƃ͂Ȃ��B
�@
���������āA�Q�P���I�ɐ����邷�ׂĂ̐l�ɏ\���ȐH���Ɛ�����������Ƃ����ڕW��B�����邽�߂ɂ́A��茫���Ȑ���A���D�ꂽ�Z�p���d�v�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ�B�܂��A�����}���āA�����l���A�܂��l�ޑS�̂��n���ɂ����Ă��鈳�͂��y�����邱�Ƃ��K�v�ł���B�n���Ƃ����V�X�e���ɑ����Ƃ��]�T���������Ȃ���A�₪�Ă͓ˑR�ɕ��Ă��܂��B�������͊�������̂ł͂Ȃ��A�Đ������A�n���̎��R�������Ԃ��̂ł͂Ȃ��A���悤�ȁA�V�������_�Ƃ̌`�Ԃ��\�z���邱�Ƃ��K�v���B
�@
�������͎��Ԃ��B���ׂĂ̐l�Ԃ��A������Ȃ��n���������ɏ�D���Ă���B���ڂƂȂ�i�����͂��ׂĂ̐l�ɓ����Ӗ������B�����āA�ωׂ��y�����邽�߂ɍs�����鎞�Ԃ́A���͂⏭�������c���Ă��Ȃ��B
�@
�Q�l�����@
�P�j���s�������E���������F�T���h���E�|�X�e�����A��������Ė�A�Ƃ̌�����i�Q�O�O�O�j
�Q�j�n�������P�X�X�X�|�Q�O�O�O�F���X�^�[�E�u���E���Ғ��A�l���T���Ė�A�_�C�A�����h�Ёi�P�X�X�X�j
�R�j�n�������Q�O�O�O�|�O�P�F���X�^�[�E�u���E���Ғ��A�l���T���Ė�A�_�C�A�����h�Ёi�Q�O�O�O�j
�S�j�n�������Q�O�O�P�|�O�Q�F���X�^�[�E�u���E���Ғ��A�G�R�E�t�H�[�����Q�P���I�ďC�A�Ƃ̌�����i�Q�O�O�P�j
�T�j�n�������Q�O�O�Q�|�O�R�F�N���X�g�t�@�[�E�t���C���B���Ғ��A�G�R�E�t�H�[�����Q�P���I�ďC�A�Ƃ̌�����i�Q�O�O�Q�j
�U�jJohannesburg Summit 2002: Global Challenge Global Opportunity, United Nations (2002)
�V�jWorld Water Vision: World Water Council, 2000, Earthscan Publication Ltd (2000)
�W�j�_�ƐV���F�_���A2003�N1��10��
�@
�@
| �@ |
�\�P�@�Q�O���I�ɂ����鐢�E�̐����p |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�P�ʁF�����R |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�P�X�O�O�N |
�P�X�T�O�N
�@ |
�P�X�X�T�N
�@ |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| �@ |
�_�� |
�搅 |
�T�O�O |
�P�C�P�O�O |
�Q�C�T�O�O |
�@ |
| �@ |
�@ |
���� |
�R�O�O |
�V�O�O |
�P�C�V�T�O |
�@ |
| �@ |
�H�� |
�搅 |
�S�O |
�Q�O�O |
�V�T�O |
�@ |
| �@ |
�@ |
���� |
�T |
�Q�O |
�W�O |
�@ |
| �@ |
���� |
�搅 |
�Q�O |
�X�O |
�R�T�O |
�@ |
| �@ |
�@ |
���� |
�T |
�P�P�T |
�T�O |
�@ |
| �@ |
�����{�� |
�������� |
�O |
�P�O |
�Q�O�O |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| �@ |
���v |
�搅 |
�U�O�O |
�P�C�S�O�O |
�R�C�W�O�O |
�@ |
| �@ |
�@ |
���� |
�R�O�O |
�V�T�O |
�Q�C�P�O�O |
�@ |
�@
�@
| �\�Q�@��ʂQ�O�J���̟��ʐςƐ��E�̍��v�A�P�X�X�T�N |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@��
�@ |
���ʐ�
�@ |
������
�k�n�̊��� |
�@ |
| �@ |
�@ |
(100���w�N�^�[��) |
(��) |
�@ |
| �@ |
�C���h |
�T�O�D�P |
�Q�X |
�@ |
| �@ |
���� |
�S�X�D�W |
�T�Q |
�@ |
| �@ |
�č� |
�Q�P�D�S |
�P�P |
�@ |
| �@ |
�p�L�X�^�� |
�P�V�D�Q |
�W�O |
�@ |
| �@ |
�C���� |
�V�D�R |
�R�X |
�@ |
| �@ |
���L�V�R |
�U�D�P |
�Q�Q |
�@ |
| �@ |
���V�A |
�T�D�S |
�S |
�@ |
| �@ |
�^�C |
�T�D�O |
�Q�S |
�@ |
| �@ |
�C���h�l�V�A |
�S�D�U |
�P�T |
�@ |
| �@ |
�g���R |
�S�D�Q |
�P�T |
�@ |
| �@ |
�E�Y�x�L�X�^�� |
�S�D�O |
�W�X |
�@ |
| �@ |
�X�y�C�� |
�R�D�T |
�P�V |
�@ |
| �@ |
�C���N |
�R�D�T |
�U�P |
�@ |
| �@ |
�G�W�v�g |
�R�D�R |
�P�O�O |
�@ |
| �@ |
�o���O���f�V�� |
�R�D�Q |
�R�V |
�@ |
| �@ |
�u���W�� |
�R�D�Q |
�T |
�@ |
| �@ |
���[�}�j�A |
�R�D�P |
�R�P |
�@ |
| �@ |
�A�t�K�j�X�^�� |
�Q�D�W |
�R�T |
�@ |
| �@ |
�C�^���A |
�Q�D�V |
�Q�T |
�@ |
| �@ |
���{ |
�Q�D�V |
�U�Q |
�@ |
| �@ |
���̑� |
�T�Q�D�S |
�| |
�@ |
| �@ |
���E |
�Q�T�T�D�T |
�P�V |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�o���FU. N. Food and Agriculture Organization,1996
Production Yearbook(Rome;1997) |
�@
�@
| �\�R�@���E�̟��n�ɂ�����y��̉��ޏW�ρi1980�N��㔼�j |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@��
�@ |
���Q������
���_�n |
���Q������
���_�n�̊��� |
�@ |
| �@ |
�@ |
(100���w�N�^�[��) |
(��) |
�@ |
| �@ |
�C���h |
�V�D�O |
�P�V |
�@ |
| �@ |
���� |
�U�D�V |
�P�T |
�@ |
| �@ |
�p�L�X�^�� |
�S�D�Q |
�Q�U |
�@ |
| �@ |
�A�����J |
�S�D�Q |
�Q�R |
�@ |
| �@ |
�E�Y�x�L�X�^�� |
�Q�D�S |
�U�O |
�@ |
| �@ |
�C���� |
�P�D�V |
�R�O |
�@ |
|
�@ |
�g���N���j�X�^�� |
�P�D�O
|
�W�O
|
�@ |
| �@ |
�G�W�v�g |
�O�D�X |
�R�R |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
| �@ |
���v |
�Q�W�D�P |
�Q�P |
�@ |
| �@ |
���E�̐���l |
�S�V�D�V |
�Q�P |
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���F�P�j
�@ |
���ޏW�ς̐��莞���Ƃقړ����A1987�N�̟��ʐϐ��l�Ɋ�Â��B�������A�E�Y�x�L�X�^���ƃg���N���j�X�^���̟��ʐς͂e�`�n�A1996 Production Yearbook�ɂ��B |
�@ |
�Q�j
�@ |
���Q���Ă�����_�n�̐��E�̐���l�ɂ��ẮA���v�̂Q�P��������ɂ��ĎZ�o�����ʐςł���B |
�@ |
| �@ |
�o���FAdapted from F.Ghassemi, A, J,Jakeman, and H, A, Nix, Salinisation
of Land and Water Resources (Sydney : University of New South
Wales Press, 1995) |
�@
�@
| �@ |
�\�S�@��̐��Y�������P���邽�߂̋Z�p�Ƒ� |
| �@ |
�@ |
�@ |
| �@ |
�J�e�S���[ |
�Z�p�^�� |
| �@ |
�Z�@�p |
�E���ϓ��ɟ�邽�߂̓y�n�̕��R�� |
| �@ |
�@ |
�E���̔z�������P���邽�߂̃T�[�W��� |
| �@ |
�@ |
�E���ϓ��Ɏ{�����邽�߂̌����I�ȃX�v�����N���[ |
|
�@ |
�@ |
�E�����ƕ��ɂ�鑹�������炷���߂̒�G�l���M�[�^�����{���X�v�����N���[ |
| �@ |
�@ |
�E�y�n�ւ̐Z���𑣐i���A�n�\���o�����炷���߂̐��ԉ� |
|
�@ |
�@ |
�E�������̑��̐����������炵�A�앨�P���𑝂₷���߂̓_�H��� |
| �@ |
�ǁ@�� |
�E���X�P�W���[���Â���̉��P |
| �@ |
�@ |
�E�K���ɐ����������邽�߂̐��H�Ǘ��̉��P |
| �@ |
�@ |
�E�앨�̒P��������Â���d�v�Ȏ����ɂ������� |
| �@ |
�@ |
�E���ۑS�^�̍k�]�@ |
| �@ |
�@ |
�E���H�Ɛݔ��̃����e�i���X�̉��P |
| �@ |
�@ |
�E�r���̍ė��p |
| �@ |
���x�@�\ |
�E�_���̎Q���Ɨ��������𑣐i���邽�߂̐����g�D�̐ݗ� |
| �@ |
�@ |
�E���⏕���̍팸����ѐߐ����i�^�̐����i�ݒ� |
| �@ |
�@ |
�E�����I�Ō����Ȑ��s��`���̂��߂̖@�I�g�g�݂̊m�� |
|
�@ |
�@ |
�E���ԕ���ɂ��������P�Z�p�̕��y�𑣐i���邽�߂̃C���t������ |
| �@ |
�@ |
�E�P���E���Ǖ��y�����̉��P |
| �@ |
�͔|�Z�p |
�E���U�����P���b�g��������̎��ʂ̍����앨�i��̑I�� |
| �@ |
�@ |
�E�y�됅�����ő���ɗ��p���邽�߂̊ԍ� |
| �@ |
�@ |
�E�C���������ї��p�\�Ȑ��̎��ɂ��K�����앨�̑I�� |
|
�@ |
�@ |
�E�y��Ɛ��̉����Z�x�����̏������Ő��Y���ő剻���邽�߂̗֍� |
|
�@ |
�@ |
�E���������R�������܂��͈��肵�Ȃ��n��ɂ������鯁i����j�ɋ����앨�̑I�� |
| �@ |
�@ |
�E�������̍����앨�i��̊J�� |
�@
�@
| �\�T�@�n�����ւ̎�v�ȋ��� |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���@��
�@ |
������
�@ |
���Z�x�ʼn������ꂽ�ꍇ��
�l�̂Ɛ��Ԍn�ւ̉e�� |
���X�N�̍�����v�n��
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�Ɏ_��
�@ |
���w�엿�̗��o�G�{�Y���A�G���������V�X�e��
�@ |
�]�ւ̎_�f������j�Q���A���c�������S�����邨���ꂪ����u���[�x�r�[�nj�Q
������n���̑��̊튯�̃K���Ɋ֘A����G����ɂ����鑔�ނُ̈푝�B�ƕx�h�{���������N���� |
�A�����J�̒������Ƒ吼�m�ݒ����A�����ؖk�����A�C���h�k���A�����[���b�p�e�n
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�_�@��
�@ |
�_��A��A�S���t�ꂩ��̗��o�G�����n����̘R�o
�@ |
�L�@���f�n�������͖쐶�����̐��B�@�\�Ɠ�����@�\�̏�Q�Ɋ֘A����G�L�@�����_�������ƃJ���o�~���_�������͐_�o�n�̏�Q�Ɗe��K���Ɋ֘A���� |
�A�����J�̈ꕔ�n��A�����A�C���h
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�����w����
�@ |
�n���������^���N
�@ |
�x���[�����̑��̐Ζ����w�����ɂ��炳���ƁA���ꂪ��Z�x�ł����Ă��K���̌����ɂȂ邱�Ƃ����� |
�A�����J�A�C�M���X�A���\�A�̈ꕔ�n��
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���f�n�n��
�@ |
�����ƃv���X�`�b�N�̒E�����G�ߗ��N���[�j���O�G�G���N�g���j�N�X���i�ƍq��@�̐��� |
���B�@�\��Q�ƈꕔ�̃K���Ɋ֘A����
�@ |
�J���t�H���j�A�B�A���A�W�A�̍H�ƒn��
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�q�@�f
�@ |
���R�E�ɑ���
�@ |
�_�o�n�Ɗ̑���Q�G�畆�K��
�@ |
�o���O���f�V���A�C���h���x���K���B�A�l�p�[���A��p |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���̑��̏d����
�@ |
�̍z��G�����n�G�L�Q�p����������
�@ |
�_�o�n�Ɛt���̏�Q�G��ӈُ�
�@ |
�A�����J�A�����A�����J�A�����[���b�p |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���ː�����
�@ |
�j�����ƈ�Ôp����
�@ |
�ꕔ�̃K���̃��X�N�����߂�
�@ |
�A�����J�����A���\�A�̈ꕔ�n��
�@ |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
�t�b����
�@ |
���R�E�ɑ���
�@ |
���ւ̉e���G�Ґ��ƍ��̑���
�@ |
�����k���A�C���h�k�����A�X�������J�̈ꕔ�n��A�^�C�A���A�t���J |
| �@ |
�@ |
�@ |
�@ |
���@��
�@ |
�C���̐Z��
�@ |
�W���������p����p�Ɏg�p�ł��Ȃ��Ȃ�
�@ |
�����ƃC���h�̉��ݕ����L�V�R�ƃt�����_�B�̘p�ݕ��A�I�[�X�g�����A�A�^�C |
�@
�@
�@
�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�R�j�F�������W�{��
�@ |
�@
�@�i�Ɓj�_�Ɗ��Z�p���������ݗ����ꂽ�����P�R�N�S���ɁA�V�����_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[���ݒu���ꂽ�B���̃Z���^�[�ɂ́A�y�땪�ތ������A���������ތ���������э������ތ������Ƃ�����B���ꂼ��̌������́A�u�y�냂�m���X�فv�A�u�������W�{�فv����сu�����W�{�فv���ێ��E�Ǘ�����ƂƂ��ɁA�����̎����������ɗ����p���Ă���B���́u�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�Q�j�v�ł́A�u�y�냂�m���X�فv���Љ���B�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�R�j�Ɓi�S�j�ł́A�u�������W�{�فv�Ɓu�����W�{�فv���Љ��B
�@
���C���x���g���[�Z���^�[�Ƃ́H
�@�C���x���g���[�Ƃ������t�́A��ʂɂ͍��Y��ɕi�̖ژ^���Ӗ����邪�A���R�����̖ژ^�A�ژ^�̍쐬�A����ɂ͖ژ^�ɋL���ꂽ���i�̈Ӗ�������B�ŋ߂ł́A�Ⴆ�u���g���K�X�C���x���g���[�v�̂悤�ɁA���R�Ȋw�n�ł��悭�g����悤�ɂȂ��Ă��Ă���B
�@
�@�_�Ɗ������������邽�߂̌����ł́A�܂��_�Ɗ����\������y��A���A��C�A�����A�������A�����A�A���A�엿�A�_��Ȃǔ_�Ɛ��Ԍn�̒��ő��݂ɍ�p�������Ă���v�f���悭�c�����邱�Ƃ��d�v�ł���B�����̗v�f�̒����E�ϑ��E���́E���j�^�����O�Ȃǂ̃f�[�^���@�A���ށE�����E�@�\�E���ԁE�\���Ȃǂ̒m���A�ۑS�E�Ǘ��Ȃǂ̋Z�p�Ɋւ�����ƕW�{�́A���N�ɂ킽�葽��̘J�͂Ǝ�����������Œ~�ς���Ă������̂ł��邵�A�_�Ɗ������𐄐i�����ł��A�܂��������ʂ��Љ�ɖ𗧂ĂĂ�����ł��A�������ɂƂ��ċM�d�ȍ��Y�ł���B
�@
�@�_�Ɗ��Z�p����������舵������H���̈��S���̖��́A���N�����Ă��킶��Ɛi�s���A�ˑR��艻���邱�Ƃ������B�n�����g���A�_�C�I�L�V���E�J�h�~�E���E�Ɏ_�����f�����A�N���E���������̐��Ԍn�e���Ȃǖ��̔����ɐv���ɑΉ����A�_�앨��_�Ɛ��Ԍn�̈��S�����m�ۂ��邽�߂ɂ́A��������K�v�ȃf�[�^��W�{���W�ς��Ă����A����𑍍��I�Ɋ��p�����������͂��K�v�ł���B
�@
�@�_�Ɗ��C���x���g���[�́A���U���ĕۑ�����Ă���_�Ɗ��ɌW���c��ȃf�[�^��W�{�����āA�f�[�^�x�[�X����i�߂�ƂƂ��ɁA�����̏��̌����E���p��V���ȏ��̒~�ς�e�Ղɍs�����Ƃ̂ł���V�X�e�����J�����邱�Ƃɂ��A������z���ď��𗬒ʂ����A���x���p�A���ʓI���p��}�邱�Ƃ��߂����Ă���B
�@
�@�܂��A�_�Ɗ��C���x���g���[�ɂ́A�W�{���d�v�ł���B���݁A�_�Ɗ��Z�p�������ɂ͍����O�̂Q�R�O�ȏ�̓y�냂�m���X�i�f�ʕW�{�j�Ƒ����̓y�뎎���A��P�Q�O���_�̍����W�{�ƂT�O�O�_����^�C�v�W�{�A��P���P��_�̔������W�{��ۊ��Ȃǂ��������A�_�Ɗ��C���x���g���[�\�z�̊�b�ƂȂ镪�ށE���茤���⌤���f�ނ̒ɖ𗧂ĂĂ���B���Ƃ��A�ߋ��ɍ̎悳��~�ς���Ă���y�뎎���́A�_�C�I�L�V���̂悤�ɐV���ɔ��������������ߋ��ɂ����̂ڂ��Ė��炩�ɂ��A�����̃��X�N�̗\�����s���̂Ɋ��p�ł���B
�@
�@�_�Ɗ��C���x���g���[�́A�����҂����łȂ��A�s���W�ҁA�Z�p�ҁA��ʎs���ɑ��Ă��K�v�ȏ���ʓI�ɒł�����A������V���ȏ��Y������A������܂��A�C���x���g���[�ɖ߂��Ă��炤���Ƃő��B����V�X�e���ɂ������ƍl���Ă���B�܂��A�_�Ɗ��̏�Ԃ��ߋ��A���݁A�����ɂ킽���Ĉ�ڂŌ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ��邱�Ƃɂ���āA���������̂Ȃ����S�Ȕ_�Ɗ�������������Ɍp�����邱�Ƃɍv���������ƍl���Ă���B
�@
�@�_�Ɗ��C���x���g���[�́A�_�Ɗ��Ɋւ�邷�ׂĂ̕���̏���W�{�̏W�ρA��ڎw���Ă���̂ŁA�_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[�����łȂ��S����̘A�g�A���͂ɂ��\�z��i�߂Ă���B���ꂪ�C���x���g���[�̓��e�ł���B
�@
���W�{�ق̑S�e
�@�����̔������W�{�ق́A�_�ѐ��Y�ȎP���̓Ɨ��s���@�l�Ƃ��Ă͗B��̔������W�{�ۑ��{�݂ł���B�����ł́A������ꂽ�������z���^�C�v�W�{�ɔ_�Ɗ��Z�p�������� NIAES No. ��t���ĕۊǂ��Ă���B����ɁA�P�W�W�O�N�ォ�猻�݂Ɏ���܂ł̖�P�Q�O�N�Ԃɂ킽��E�̏W���ꂽ�����������W�{�A���������������t�W�{�Ȃǖ�T�C�O�O�O�_���A�W�{�����ň���I�ɕۊǂ��Ă���B
�@
�@��������̋L�ڂ��s���ۂɁA�����̕W�{�͊w�p�I�ɉ��l�������A�O������̗��p�҂������B�܂��A�_�ѐ��Y�Ȕ������W�[���o���N���Ƃ̈�Ƃ��āA�ۂ���ю���ۂ̓��������A���v���A�����`���[�u�A�p��|�{�����ǂȂǍ��킹�Ė�S�C�O�O�O�_���ቷ���ɕۑ�����Ă���B����͔����������W�{�𒆐S�Ƀf�[�^�x�[�X���쐬���A�l�b�g��ʂ��č����O�ɏ������J���A�������W�{�̗L�����p�𑣂��\��ł���B
�@
�@�����ł́A�������z���^�C�v�W�{���ۊǂ��Ă���B�������z���^�C�v(holotype)�W�{�Ƃ́A�������̐V�킪�L�ڂ����Ƃ��A���̒��҂��w�肷�鐳��W�{�ŁA���̔������|�{�̂��邢�͐A�������̂̊����̂Ƃ��ĕۑ��������̂ł���B���̕W�{�قł́A���݂̂Ƃ���ȉ��̕\�Ɏ������X��̔������̃z���^�C�v������B�����́A�ݔ��ɂ��Ꮌ�̍œK�����Ō��d�ɕۊǂ���Ă���B�܂��A������̗v��������A�����ȕW�{�فiherbarium)�Ƃ��Ă��̂悤�ȕW�{�������̐��𐮂��Ă���B
�@
�@�܂��A�z���^�C�v�Ƌ��ɃA�C�\�^�C�v(Isotype�F����W�{�A�d���W�{�j�������ɕۊǂ��Ă���B�����̊�W�{�́A��������̓���ɂ͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł���B������ۊǂ��邱�Ƃ́A���̕W�{�ق̏d�v�ȋƖ��̈�ƂȂ��Ă���B
�@
| ����������������z���^�C�v�W�{ |
| �@ |
| �W�{No. |
�ۊw�� |
�a�� |
����� |
Isotype�� |
| NIAES10463 |
Exobasidium japonicum
�@ |
���}�c�c�W���������a�� |
�]�ˏ��T
�@ |
�|
�@ |
| NIAES10472 |
E. cylindrosporum
�@ |
���`�c�c�W�����a��
�@ |
�]�ˏ��T
�@ |
�|
�@ |
| NIAES10477 |
E. kawanense
�@ |
���`�c�c�W�������a�� |
�]�ˏ��T
�@ |
�|
�@ |
| NIAES10494 |
E. otanianum
�@ |
�R�o�m�~�c�o�c�c�W���������a�� |
�]�ˏ��T
�@ |
�|
�@ |
NIAES
�@ |
Cercospora rhapisicola
�@ |
�J���m���`�N���_�a�� |
�x�i���C
�@ |
�R
�@ |
NIAES
�@ |
Macrophoma aspidistrae |
�n�������_�a�� |
��c�g�l |
�| |
| NIAES20510 |
Claviceps sorghicola
�@ |
�\���K�����p�a��
�@ |
�������Y
�@ |
�|
�@ |
| NIAES20515 |
Fusarium fractiflexum
�@ |
�\�@
�@ |
�؍F�V
�@ |
�R
�@ |
| NIAES99701 |
F .kyushuense
�@ |
�R���M�Ԃ��ѕa��
�@ |
�؍F�V
�@ |
�R
�@ |
�@
�������������t�W�{
�@���̕W�{�قł́A��W�{�̑��ɖ�R�C�O�O�O�_�̔����������W�{��ۊǂ��Ă���B���̑����͂����t�A�܂���������A���t�Ɋ���������Ԃʼn����t�Ƃ��Ċ���������Ԃŕۊǂ���Ă���B���������W�{�́A�z�����ɕ��Ŋ����A�����邢�͔������̕��ނ��ƂɕW�{�ɂ̒��ɑ̌n�I�ɐ����E�ۊǂ���Ă���B�����̕W�{�̒��ɂ́A�P�W�W�O�N��� Lagerheim, Sydow ����Ɏn�܂���{�A���a���w���t�����������M�d�ȊR���N�V�������܂܂�Ă���B����́A�����������f�[�^�x�[�X�����A���܂��܂Ȍ`�ŏ�����Ă����\��ł���B�Ȃ��A��]���錤���҂ւ̑ݏo���s���Ă���B
�@
| �����������Ȕ����������t�W�{ |
| �@ |
| �� |
�R���N�V�������e�i�ۑ����j |
�̏W���� |
�W�{�� |
| Lagerheim. G. V. |
Entyloma, Uromyces |
1887-1901 |
28 |
| Sydow. P. |
Puccinia, Urocystis, Ustilago |
1896-1902 |
97 |
| �͑��h�g |
Botrytis, Cercospora,�@Pyricularia |
1911-1943 |
255 |
| �ꌳ���� |
Xanthomonas, Alternaria, Colletotrichum |
1913-1942 |
54 |
| �c�����i |
Peronospora, Phytophthora, Sclerospora |
1919-1042 |
70 |
| �����R�G�� |
Phyllosticta, Sclerotium |
1920-1946 |
32 |
| �y���s�v |
Curvularia, Scolocotrichum, Stagonospora |
1956-1970 |
212 |
�@
���ۑ��ꏊ
�h�D�����W�{�i���Ɋ������́j�F
�P�D�����������t�W�{�F��5,000�_�i�ۑ��ꏊ�F�������W�{�فj
�Q�D�������|�{�W�{�i�|�{�W�{�������������́j�F��2,000�_�i�ۑ��ꏊ�F�������W�{�فj
�@
II�D�����Ă����ԁi���ɐ����́j�F����ہA�ۍ��킹�Ė�4,000�_
�P�D����ۂ̕ۑ��ۊ��F��1,000�_�i�ۑ��ꏊ�F�������W�{�فj
���s���̎��̂ɔ����āA����ۊ��������Ǖۑ��ƁA�k�����W�{�ۑ����ĊǗ����Ă���B����ɁA�����Ǖۑ��A�k�����W�{�ۑ�������ۂ𒆐S��100�ۊ����x�ɂ��āA�t�̒��f�œ����ۑ����Ă���B
�Q�D�ۂ̕ۑ��ۊ��F��3,000�_�i�ۑ��ꏊ�F�������W�{�فA�{�ٔ��������ތ������i�R�P�R�j�A�艷�|�{���Q�i�R�O�S�j
���s���̎��̂ɔ����āA����ۊ����R�����ɕ����ĕۑ����Ă���B�������W�{�فi���������ۑ��j�A���������ތ������i�R�P�R�j�i�����ۑ��j�A�艷�|�{���Q�i�R�O�S�j�i���������ۑ��j
�@
���Q�l����
�������W�{�فF�C���x���g���[�A�_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[�A��P���A57-56�i2002)
�@
���₢������F�_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[�@���������ތ�����
�d�b�F029-838-8355�A�@E-mail : seya@niaes.affrc.go.jp
�@
�@
�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�S�j�F�����W�{��
�@ |
�@
�@�i�Ɓj�_�Ɗ��Z�p���������ݗ����ꂽ�����P�R�N�S���ɁA�V�����_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[���ݒu����A���̃Z���^�[�ɂ́A�y�땪�ތ������A���������ތ���������э������ތ������Ƃ�����A���ꂼ��̌������́A�u�y�냂�m���X�فv�A�u�������W�{�فv����сu�����]�{�فv�����L���Ă��邱�ƂƃC���x���g���[�̓��e�ɂ��ẮA���łɂ��̍��́u�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�R�j�v�ŏЉ���B�܂��A�u�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�Q�j�v�ł́u�y�냂�m���X�فv���A�u�_�Ɗ��Z�p�������ē��i�R�j�v�ł́A�u�������W�{�فv���Љ�Ă����B�����ł́A�u�����W�{�فv���Љ��B
�@
�@�_�Ɗ��Z�p�������̖{�ق̗����ւ��o��ƁA�E���ɍג����Q�K���Ă̕ʓ�������B�t�ɂȂ�ƁA�F�����L���ȃc�c�W�����̕W�{�ق̌��ւ����藧�Ă�B�P�K�ƂQ�K�ɂ́A�����R�Q�N�i�P�W�X�X�j�ɔ_��������ɍ��������ݗ�����Ă���A����܂Œ��N�ɂ킽���Ď��W����Ă��������W�{���������ƕۑ�����Ă���A���̐��͌��ݖ�P�Q�O���_�ɂ̂ڂ�B�܂��A�T�O�O��ɂ���ԃz���^�C�v�W�{���ۊǂ���Ă���B�P�K�͌�������̃I�t�B�X�����˂Ă���̂ŎG�R�Ƃ��Ă��邪�A�����̔M�C����������B�Q�K�͂܂��ɕW�{�ق��̂��̂ŁA���@�I�ȃX�`�[�������R�ƕ��сA���̒��ɂ͖����̕W�{�������Ă���B
�@
�@�����͔_�Ɗ����\������d�v�ȗv�f�̂ЂƂł���B���܂��܂ȍ����ނ��錤���́A�����ɂ�����邠���錤���̊�b�ł�����B���̌������̍������ތ������ł́A�_�ƋZ�p�������i�P�X�T�O�N�ɐݗ��j�̍�����_�ƊQ���A�V�G�A�ԕ��}����Ȃǔ_�ƂɊW���鍩���ނ𒆐S�Ƃ��āA���ނ̌������s���Ă����B�_�Ɗ��Z�p�������i�P�X�W�R�N�`�j���ݗ�����Ă���́A�_�Ƃ̐��Y�̏�ʂ����ł͂Ȃ��_�Ɗ��S�̂ɂ��������̂Ɍ����̑Ώۂ��L���Ă������B
�@
�@�����W�{�قƂ����A�`���E�A�g���{�A�N���K�^�Ȃǂ̑�`���퍩���Ⓙ����Ȃǂ�W�����邽�߂̊فA�������͒P�Ȃ��Ƃ��ďW�߂�ꂽ���̂�W������قƎv�������ł��邪�A���̕W�{�ق̕W�{�͂��̂悤�ȈӐ}�Ŏ��W���ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�����ł̕W�{�́A��{�I�ɂ͌`�ԏ��Ɋ�Â����ތ����̍ޗ��Ƃ��邽�߁A���邢�͎�̓���̎Q�ƕW�{�Ƃ��邽�߂ɕۊǂ���Ă���B����Ɍ`�ԏ��ȊO�ɂ��A���̍����̕��z�A�H���A���������A�̏W�����̊������A�c�m�`�ȂǁA�W�{���璊�o�ł�����𑽊�ɂ킽��ۑ����Ă���̂ŁA�H�v����ŗl�X�Ȍ����ɗ��p���邱�Ƃ��ł���B���̍����W�{�قł́A����܂Œ��N�ɂ킽���Ď��W����Ă��������W�{��ۑ����Ă���A���̐��̑����͌��ݖ�P�Q�O���_�ɂ̂ڂ�B
�@
���W�{�ق̕W�{���e�\�͂ƌ���
�@���̌������̕�̂ł���_�������ꂪ�ݗ����ꂽ�̂́A�����Q�U�N�i�P�W�X�R�j�ł���B�ݗ��U�N��̖����R�Q�N�i�P�W�X�X�j�ɂ́A���������݂���ꂽ�B���̍����W�{�قɂ́A���������ݗ�����Ĉȗ��̕W�{���~�ς���Ă���B�_��������͏��a�Q�T�N�i�P�X�T�O�j�̋@�\���v�ɂ��_�ƋZ�p�������ƂȂ�A���݂̌������̑O�g�ł��鍩�����ޓ��茤�������V�݂��ꂽ�B
�@
�@���̓����͕ۊǂ��邽�߂̕������Ȃ����߁A�W�{�͕W�{���ɓ����ꌤ�����̂Ȃ��ɎG�R�Ɠ�����]�V�Ȃ�����Ă����B�������ɂ������_�ƋZ�p�������́A���a�T�S�N�i�P�X�V�X�j�ɒ}�g�w���s�s�ֈړ]�����B���̈ړ]�ɍۂ��ĕa�������W�{�ق����Ă��A�������ތ������Ɖ������ꂽ�����������̊ق��Ǘ����Ă����B
�@
�@�a�������W�{�ق̓����́A�a���W�ƍ����W�̃X�y�[�X�ɕ�����Ă���B�����W�̃X�y�[�X�͍������ޕW�{���R���A�����t�Z�W�{���A�^�C�v�W�{���A���ԁE�˗�����W�{���ȂǂR�W�O�u�̍L�������B�����T�N�i�P�X�X�R�j�ɂ́A���̊قɗאڂ��Ċ��������̓Z���^�[�����Ă��A���̂Q�K�ɐV���ɂQ�Q�O�u�̍����W�{�ۑ������݂���ꂽ�B���ꂪ���݂̍����W�{�ق̎p�ł���B
�@
�@���݁A�����W�{�قɂ͑�^�h�C�c�^�W�{���S�S�����[�ł���W�{���b�J�[���Q�S�W��ݒu����Ă���B���ɂ��^�C�v�̈قȂ�W�{���b�J�[���A�܂������{�ق̌������ɂ���̕W�{���b�J�[������̂ŁA�������܂߂�ƑS�̂Ŗ�P�Q�C�O�O�O���̕W�{�������[�ł���ݔ�������B�P�������蕽�ςP�T�O�_�̕W�{���[�߂���Ɖ��肷��ƁA��P�W�O���_�̕W�{��ۊǂł��邱�ƂɂȂ�B���݂��łɖ�V�C�O�O�O���ɕW�{���[�߂��Ă���̂ŁA���L�̊����W�{���͂P�O�O���_�]��Ɛ��肳���B
�@
�@��q�����W�{�ȊO�ɁA����݁i�O�p���j�ɓ�������Ԃ̕W�{������������̂ŁA���̎����͖��炩�ł͂Ȃ��B�����ɂ��Ă͏����W�{�쐻���s���\��ł��邪�A���N�V���ɍ̏W���ꂽ������W�{�̏����ɒǂ��A�O�p���W�{�̐����͂Ȃ��Ȃ��i��ł��Ȃ��̂�����ł���B�܂��g�̂̓�炩��������ۑ����邽�߂̃A���R�[���t�Z�W�{���ۑ����Ă���B�t�Z�W�{���ɂ̓`���E�ڂ�n�G�ڂ���̂Ƃ���c���W�{�������ۊǂ���Ă��邪�A���̐��m�Ȑ��͌��݂̂Ƃ���c���ł��Ă��Ȃ��B����ɃA�u�����V��J�C�K�����V�A�A�U�~�E�}�Ȃǂ̔��������͌������Ō������邽�߂̃v���p���[�g�W�{�Ƃ��ĕۊǂ���Ă���B��͂萳�m�Ȑ��͕s���ł��邪�A�v���p���[�g�P�O�O��������[�P�[�X�Ŗ�U�O�O���A�Q�T�����P�[�X�Ŗ�W�O�����ۊǂ���Ă���B
�@
�@�ȏ�̊����W�{�A�O�p���W�{�A�t�Z�W�{�A�v���p���[�g�W�{�̂��ׂč��킹��ƁA�����W�{�̐��͖�P�Q�O���_�ɂ̂ڂ�Ɛ��肳��A���N��Q���_���������Ă���̂�����ł���B
�@
�������W�{�̓��e
�@�W�{�قɂ͗l�X�ȓ��������R���N�V������W�{�V���[�Y���ۑ�����Ă���B���̎�Ȃ��̂ɂ��ďЉ��B
�@
�P�j�����R���N�V�����F�����W�{�ɂ́A���������̃X�^�b�t�����猤���ΏۂƂ��鍩���Q�N�ɂ킽���Ď��W�������̂̂ق��A�O���̌����҂��瓖�W�{�قɊ��ꂽ�R���N�V�����������܂܂��B�����̃R���N�V�����́A���ꂼ��̌����҂�����̐�啪��𒆐S�Ƃ��ē���̖ړI�������ďW�߂����́A���邢�͓���n��̍������f�������̂������A�����ޗ��Ƃ��Ă悭�܂Ƃ܂��Ă���A�w�p�I�ɂ����l�̍������̂ł���B���ݏ������Ă����ȃR���N�V�������\�P�ɏЉ��B
�@����͍ŋ߂T�N�ԂɐV���Ɋ��ꂽ���́B�����G�Y�A�����͕v�A���ɘY�̊e�R���N�V�����ɂ��Ă͌��݂������W�{���ڊǒ��ŁA���コ��ɓ_���͑�������\��B
�@
| �\�P �����W�{�ق̎�ȏ����R���N�V�����i�\�����j |
| �@ |
�@ |
| �҂܂��͌����� |
�R���N�V�����̓��e
�@ |
| �Έ�@�@�� |
�R�o�`�ނ���Ƃ����I�Ɠ���A�W�A�̍��� |
| ���@�@�� |
�V���N�K�Ȃ���у��C�K�Ȃ̕W�{�U�T�V�_ |
| ����푾�Y |
���݂ł͍̏W�s�\�ȓ����Y�����Ȃ� |
| ���ہ@�M�F |
�b���E�`���E����Ƃ������E�̔��퍩�� |
| �����@�u�N |
���n�`�ڂ𒆐S�Ƃ����W�{��P�V�C�T�O�O�_ |
| �����@�Õv |
�n�`�ڕW�{�V���[�Y |
| �͓c�@�@�} |
�K�ނ̐�������їc���W�{��P���_ |
| �F��@���` |
�k�A���v�X�̍��R�����𒆐S�Ƃ����W�{ |
| ���F��@���` |
�����O�̍b���W�{��T�C�O�O�O�_ |
����O���v
�@ |
�A�U�~�E�}�ڂ̃v���p���[�g�W�{�Ɗ֘A����
�i�^�C�v�W�{61�_���܂ޖ�T�C�O�O�O�_�j |
�K���ɔV�g
�@ |
�J�C�K�����V��Ȃ̃^�C�v�W�{���܂ރv���p���[�g����ъ����W�{��T�C�O�O�O�_�i���l�A���h�u�����ڊǁj |
| �K�R�@�@�o
|
��瓇�Y��������уE�X�o�J�Q���E�ځA�V���A�Q���V�ڂ̕W�{�i�^�C�v�W�{�T�Q�_���܂ނR�C�Q�O�O�_�A�k�C���_�Ǝ�������ڊǁj |
| �������@�͕v |
���K�Ȃ𒆐S�Ƃ��������ڕW�{��W�C�S�O�O�_ |
| �f�@���� |
�n�i�A�u�ȁA�~�o�G�Ȃ���уA�u�Ȃ̃^�C�v���܂ޕW�{ |
| �����@�@�ɘY
|
���K�Ȃ���уV���`�z�R�K�ȂȂǂ̃^�C�v���܂ޗ����ڕW�{��Q�X�C�O�O�O�_ |
| �����@�@�O |
�u���Ȃ���уA�u�Ȃ̕W�{����ъ֘A���� |
| ��@���� |
�A���ޕW�{��Q���_ |
| ���R�@�@�� |
�A���Ȃ̃^�C�v�W�{�V���[�Y |
| �������@�G�Y |
�V���N�K�ȁA�X�Y���K�ȓ��̗����ڕW�{��P�W�C�O�O�O�_ |
| �V���@�P�� |
�H�ސ��b���L�m�R���V�ށA�L�N�C���V�ނ̕W�{����_ |
| �앣�@�@�P
|
�����O�̐H�ސ��b���L�m�R���V�ށA�L�N�C���V�ނ̃^�C�v���܂ޕW�{��T���_ |
| ���J��@�m |
�J�����V�ނ���Ƃ����W�{ |
| �����ɑ^�q |
�M�уA�W�A�Y���܂ޗ����ڗc���̉t�Z�W�{ |
| �y���@��\ |
�S�~���V�Ȃ���уA�V�u�g�R�o�`�Ȃ̃^�C�v�R�S�O����܂ޕW�{�V���[ |
| ����@���� |
���{�Y�A�u�Ȃ̃^�C�v���܂ޕW�{ |
| �����@��j |
�n�G�ڂ���уo�b�^�ڂ̕W�{ |
| �����@�r�F |
���{����ѓ���A�W�A�Y�J�~�L�����V�Ȃ���ё��̍��������_ |
| ��@���j |
�����嗤�Y���܂ރo�b�^�ڍ��� |
| ���@�m�� |
���̊Q���Ƃ��̊I�Ȃǖ�Q���_ |
| ����@�[�� |
�n���V�Ȃ���Ƃ������� |
�@
�Q�j�z���^�C�v�W�{�F�z���^�C�v�W�{�͐V�킪���߂ċL�ڂ��ꂽ�ۂɎw�肳�ꂽ�P��̕W�{�ŁA���̎�̎포����S���ƒ�߂�ꂽ���̂ł���B���ތ�����i�߂��ł͕K���Q�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�v�ȕW�{�ł���A�܂����ꂼ��̎�ɂ����P�̂������݂��Ȃ��ɂ߂ċM�d�ȕW�{�ł���B
�@
�@�W�{�قɂ́A���݂̂Ƃ���T�O�O�킠�܂�̃z���^�C�v�W�{����������Ă���B�����́A�s���̍ЊQ�����邽�ߑωE�ϐk�\�������^�C�v�W�{���̊��ȕW�{���b�J�[�ɓ�����ĕۊǂ���Ă���B�܂��A��ʕW�{�̒��ɂ��܂������̃z���^�C�v�W�{���C�t����Ȃ��܂ܕ��ꍞ��ł�����̂ƍl������̂ŁA�����ɂ��Ă����㑁�}�ɒT�����A�^�C�v�W�{���Ɉڂ��K�v������B
�@
�@���łɃ^�C�v�W�{���Ɉڂ���Ă���z���^�C�v�W�{�ތQ�ʂɌ���ƁA�b���ڂ��ł������Q�R�V��A�����Ńn�`�ڂW�S��A�n�G�ڂW�Q��A�J�����V�ڂT�W��A���̑��̏��ƂȂ��Ă���B�����̃z���^�C�v�W�{�ɂ��ẮA�w���A�a���A�̏W�f�[�^�A�L�ڕ�������łɃf�[�^�x�[�X�Ƃ��Ă܂Ƃ߂��Ă���B����͊e�z���^�C�v�W�{�̉摜����t�������ėL�p�ȕ��ޏ��f�[�^�x�[�X���쐬���A�C���^�[�l�b�g��ʂ��Đ��E�ɒ��邱�Ƃ��v�悵�Ă���B
�@
�R�j����˗��W�{�F�O���̋@�ւ��疈�N�����̓���˗��̗v��������i�\�Q�j�B�s���{���̔_�Ǝ�����▯�ԉ�Ђ���˗��������̂������A���̂قƂ�ǂ͔_�ƊQ����s���Q���ł���B�ŋ߂ł͐H�i�ɍ��������������������Ă���B����˗��̕W�{�́A���㓯�l�̈˗����������ꍇ�̎Q�l�Ƃ��邽�߁A����I���̌���˗��҂ւ͕ԋp�����W�{�قŕۊǂ��邱�Ƃ���{���j�Ƃ��Ă���B���̂��ߔN�X�����̕W�{�Ƃ��̔����Ɋւ����~�ς������A���̗ʂ͌��݂ł͂��Ȃ�c��Ȃ��̂ƂȂ��Ă���B���N�ɂ킽���Ē~�ς��ꂽ�����̕W�{�Ə���L���Ɋ��p���邽�߁A�~�Ϗ��̃f�[�^�x�[�X�������ݐi�߂Ă���Ƃ���ł���B
�@
| �@ |
�\�Q�@�ŋ߂U�N�Ԃ̓���˗����� |
�@ |
| �@ |
�N�x |
��t���� |
�W�{�� |
�@ |
| �@ |
1996 |
147 |
3168 |
�@ |
| �@ |
1997 |
133 |
1998 |
�@ |
| �@ |
1998 |
138 |
2885 |
�@ |
| �@ |
1999 |
65 |
787 |
�@ |
| �@ |
2000 |
129 |
1641 |
�@ |
| �@ |
2001 |
64 |
1151 |
�@ |
�@
�S�j�؋��W�{�F�������ʂ�_�����ɔ��\�����ꍇ�A�����ň������ޗ����؋��W�{�ivoucher specimen�j�Ƃ��ĕۑ����Ă������Ƃ��]�܂��B������̓���ɂ͊ԈႢ���N���肤����̂ł���A�^�����������Ƃ��ɂ͍Ē������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���ތ����̐i�W�ɂ���ē����P��Ǝv���Ă������̂���N������ɕ�������邱�Ƃ��������Ȃ��A�����ޗ��̍ē��肪�K�v�ɂȂ�ꍇ������B���̂悤�ȏɑΉ����邽�߂ɂ́A�����ň������ޗ��������̕W�{�ٓ��ŕۑ����Ă����K�v������B�ŋ߂ł͏؋��W�{�̕ۑ���_���̏����Ƃ��Ă���w�p�G��������B�ȏ�̊ϓ_����A���̕W�{�قł͗v��������Ώ؋��W�{�̕ۑ����t���Ă���B�킪���ł͂܂��؋��W�{�̕K�v���Ɋւ���F�����Ⴍ��t�����͑����Ȃ����A��O�����̃T���v�����z�����œ���ꂽ�̂Ȃǂ��ۑ�����Ă���B
�@
���W�{�ق̗��p��
�@�������X�^�b�t�����p����W�{�͏����W�{�̈ꕔ�ł���A�X�^�b�t�ɂ�闘�p�����ł͖�P�Q�O���_�̏����W�{�̉��l���\���ɐ����������̂ł͂Ȃ��B�����œ����ł́A��]������ΊO���̌����҂ɂ����p�������A�����W�{�╶���ނ̌����I���p��}���Ă���B�W�{�قɒ��ڗ��K�����ŋ߂U�N�Ԃ̗��p�Ґ����\�R�Ɏ������B�O���l���܂߂Ė��N�Q�O�`�T�O���̗��p������B�Ȃ��ɂ͂R�T�Ԉȏ�ɋy�Ԓ������p�̗������B�����̒������p�́A�������������x�A�˗����������x�A�����̊e�팤�C���x�A�O���l�����҂̊e�폵�ւ����x�ɂ���đ؍݂��������҂ɂ����̂ł���B���ꂼ��̕��ތQ�̐��ƂɕW�{���p�̕ւ�}�邱�Ƃ́A�����W�{�̕��ށE������i�߂��ł��L�v�ł���B
�@
| �@ |
�\�R�@�ŋ߂U�N�Ԃ̕W�{�ق̌������p�Ґ� |
�@ |
| �@ |
�N�x |
�������p�Ґ��� |
�Z�����p�Ґ� |
���p�Ґ����v |
�@ |
| �@ |
1996 |
4(1) |
18 |
22(1) |
�@ |
| �@ |
1997 |
4(1) |
42(1) |
46(2) |
�@ |
| �@ |
1998 |
3(2) |
38 |
41(2) |
�@ |
| �@ |
1999 |
3(1) |
46 |
49(1) |
�@ |
| �@ |
2000 |
4(2) |
22(3) |
26(5) |
�@ |
| �@ |
2001 |
1 |
29 |
30 |
�@ |
�� ���������A�˗������ȂǂR�T�Ԉȏ�̗��p�Ґ��B
( )�͂��̂����̊O���l���p�Ґ��@�@�@�@�@�@�@�@ |
�@
�@�܂��A�����̂��߂̕W�{�̑ݏo���͌��I�ȕW�{�ۑ��@�ւ̐Ӗ��ł���A�W�{�̗L�����p��}���ł��d�v�ł���B���N�P�O�`�Q�O���̑ݏo�˗�������A�ݏo�W�{���̓z���^�C�v�W�{���܂߂Ė��N���S�`����̂ɋy�ԁi�\�S�j�B
�@
| �@ |
�\�S�@�ŋ߂U�N�Ԃ̕W�{�ݏo�� |
�@ |
| �@ |
�N�x |
���v���� |
�W�{�� |
�@ |
| �@ |
1996 |
19( 4) |
1351(143) |
�@ |
| �@ |
1997 |
17( 3) |
1607(138) |
�@ |
| �@ |
1998 |
6( 2) |
162(�@8) |
�@ |
| �@ |
1999 |
11( 1) |
2412(650) |
�@ |
| �@ |
2000 |
9 |
306 |
�@ |
| �@ |
2001 |
15 |
867 |
�@ |
| �@ |
�v |
77(10) |
6705(939) |
�@ |
| ( )�͂��̂����̊O���ւ̑ݏo�� |
�@
�@���݂̂Ƃ���A�����W�{�ق̏����W�{�̓`���E�A�b���A�n�`�A�n�G�A�o�b�^���̖ځiorder)���x���ő�܂��ɐ�������Ă���A�����I�ɂ͂���ɉȁifamily�j���x���������͑�(genus�j���x���܂Ő�������z��Ă���B�������A�S�̓I�Ɍ���Ε��ޑ̌n�ɉ����������͂���߂ĕs�\���ȏ�Ԃł���B
�@
�@�����W�{�������̃O���[�v�̕W�{��T�����Ƃ���ꍇ�A����ł͏�q�̃R���N�V�����̒����炻�̏��ɗ����ĒT�����邱�Ƃ������A����ȊO�̏ꏊ�ɔ[�߂��Ă���W�{�ɂ��ẮA�ЂƂЂƂ̕W�{�����m�F���Ă����ȊO�ɕ��@���Ȃ��B���̂��߁A���l�̂���W�{���������̂܂ܖ�����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��ƍl�����A�������������̕W�{�Ȃǂ��ۊǂ���Ă���ɂ�������炸�A�����̕W�{��W�{��\���ɐ�������Ă���Ƃ͌����������B�����W�{�Ƃ��̏���L���Ɋ��p���邽�߂ɂ́A�W�{�̕��ނƐ����𑁋}�ɐi�߁A���Ȃ��Ƃ��Ȃ������͏�ȁisuper family)���x���܂ŕ��ށE�������A�����Ɋ܂܂��W�{���ʂɃf�[�^�x�[�X�����A�ȈՂɌ����ł���V�X�e�����\�z����K�v������B
�@
�@���̂��Ƃ��������邱�Ƃɂ���āA���̕W�{�ق̉��l������ɍ��߁A���܂��܂Ȍ����ɗL���Ɋ��p�ł�����̂ɂ��Ă��������ƍl���Ă���B
�@
�Q�l����
�P�j�����@�@�Y�i1996�j�F�_�Ɗ������Ƃ��Ă̍����W�{�A�_�Ɗ��Z�p����������V���[�YNo.�R�F20pp.
�Q�j�����@�@�Y�i1997�j�F�_�Ɗ��Z�p�����������W�{�ف|�_�Ɗ������Ƃ��Ă̍����R���N�V�����A�����Ǝ��R32�i13�j�F41-44�A
�R�j�����@�@�Y�i2000�j�F�_�Ɗ��Z�p�����������W�{�ف|�������Ƃ��Ă̍����W�{�̎��W�E�ۑ��A�n������Y�E�����`�G�ҁ@�V�ō����̏W�w�A��B��w�o�ʼn�A�����A692-706
�S�j�_�ƋZ�p���������\�N�j�҂���ψ���ҁi1974�j�F�_�ƋZ�p���������\�N�j�A�_�ƋZ�p�������A724pp�D
�T�j�����W�{�فF�C���x���g���[�A�_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[�A��P���Ap.52-56�i2002)
�@
�₢���킹��
�_�Ɗ��C���x���g���[�Z���^�[�@�������ތ�����
�d�b�F029-838-8354�AFAX�F029-838-8354�A
E-mail : kyasuda@niaes.affrc.go.jp
�@
�@
�N�������̕��z�g��ƌi�ϐ��Ԋw
�@ |
The Landscape Ecology of Invasive Spread
Kimberly A. With, Conservation Biology, 16, 1192-1203 (2002) |
�@
�@�_�Ɗ��Z�p�������́A�_�Ɛ��Ԍn�ɂ����鐶���Q�W�̍\���Ƌ@�\�𖾂炩�ɂ��Đ��Ԍn�@�\���\���ɔ���������ƂƂ��ɁA�N���E���������̐��Ԍn�ւ̉e�����𖾂��邱�Ƃɂ���āA���Ԍn�̂������h�~�A�������l���̕ۑS�Ȃǐ������̈��S��}���Ă������Ƃ��d�v�ȖړI�̈�Ƃ��Ă���B���̂��߁A�_�Ɛ��Ԍn�ɂ����鐶�����̈��S�ɊW����ŐV�̕����������W���Ă��邪�A����͐N��������̕��z�g��ƌi�ύ\���Ƃ̂������ɂ��Ă̘_���̈ꕔ���Љ��B
�@
�@�����̐����ꏊ�̏����╪�f�A����ɂ͊O�������̐N���́A�������l���ɑ���ő�̋��ЂƂȂ��Ă��邪�A�i�ς̍\���ɋy�ڂ��e���A����ʓI�ɂ͋�ԓI�z�u���N�������̕��z�g��ɋy�ڂ��e���A�ɂ��Ă̗��_�I�������邢�͌o���I�����͂ق�̏��������Ȃ��B
�@
�@�i�ϐ��Ԋw�ł́A��ԓI�z�u�����Ԋw�I�ȉߒ��ɂǂ̂悤�ɉe�����邩����������B�N�������̕��z�g��Ɋւ���i�ϐ��Ԋw�ɂ́A�����ꏊ�̕��f�⎑���̕��z�Ȃǂ̋�ԓI�z�u���A�N���̉ߒ��̂��܂��܂Ȓi�K�ɂǂ̂悤�ɉe�����邩�𗝉����邱�Ƃ��܂܂�Ă���B
�@
�@�N�������̕��z�g�����Q�W�̐N������₷���́A�i�ς̍\���ɂ���āA���̂悤�ȉe������ł��낤�B
�i�P�j�i�ςւ̂�������������E�l����ƁA�N�������̕��U��}��鐶���i��q���U�z���铮���Ȃǁj�ɑ���i�ύ\���̉e���ɂ���āA���ړI���邢�͊ԐړI�ɕ��z�g�傪���i�����B
�i�Q�j�i�ς̍\�����A�N���̉ߒ��̂��܂��܂Ȓi�K�i���Ƃ��Ε��U�ƌ̐������j�ɁA�قȂ��������A�ꍇ�ɂ���Ă͋t�����̉e����^����B
�i�R�j�i�ς̍\���ƐN�������̕��z�̑��ݍ�p�ɂ���āA���z�g�傪���i�����i�����ꏊ�̕��f�ɂ���Ď��ӕ��ɑ����̏����̌Q���`������A����炪���z�g��𑣐i����j�B
�i�S�j�i�ύ\���̕ω��ɂ���āA�����Q�W�ւ̐N�����e�ՂɂȂ�悤�ȕ����ɁA������Ԃ̑��ݍ�p�����܂�����ω������肷��i���ӌ��ʂȂǁj�B
�i�T�j�i�ς����f�����ƁA�N����j�~����ݗ������̓K���\�͂���߂�ꂽ��A���邢�́A�N�������̓K���I�Ȕ������������ꂽ�肷��B
�i�U�j�������ɂ���č��o�����ϓ��ƌi�ύ\���Ƃ̑��݉e���ɂ���āA���p�\�Ȏ����ɋ�ԓI�E���ԓI�ȕϓ��������A���Ԍn�ւ̐N���������₷���Ȃ�B
�@
�@�N�������̕��z�g��Ɋւ���i�ϐ��Ԋw�𗝉����邱�Ƃɂ���āA�N�������̕��z�g���}��������A�����Q�W�̐N������₷�����ŏ����ɂ��邽�߂̌i�ς̊Ǘ��╜���ɂ��āA�V����������ڕW�B���̋@������炳��邾�낤�B
�@
�@
�u���F�_�ƂƊ��v�̃A�N�Z�X�F
�P�P�P�C�P�P�P
��ڂ̕��ɁI
�@ |
�@
�@�u���F�_�ƂƊ��v�́A���̓��O�̔_�ƂƊ��ɂ������������m�点����y�[�W�Ƃ��āA�����P�Q�N�T���P���ɊJ�݂���܂����B���̌�A�����P���ɁA�ǎ҂݂̂Ȃ��܂ɍŐV�̏���������āA����łR�S���ɂȂ�܂����B���̊ԁA�Q�N���ȏ�̍Ό����o�߂��܂����B�ŏ��̂P�����̃A�N�Z�X�͂U�V�U���ł������A���N�o�߂����V���ɂ́A�P�C�S�P�Q���ɑ������܂����B�P�N�o�߂��������P�R�N�̂T���ɂ͂Q�C�W�R�X���ɏ㏸���܂����B���̌���A�A�N�Z�X���͏㏸�������A��N�P���ɂ͂S�C�U�X�U���ɂ��Ȃ�܂����B����Ɏ�̕������݂͂���܂����A��N�V������́A�P����������T�C�O�O�O����������A�N�Z�X�������Ă��܂��B
�@
�@���̌��ʁA���A�N�Z�X�����͂P�����ɂP�O�O�C�O�O�O���ɒB���悤�Ƃ��Ă��܂��B�����ŁA����͂P�P�P�C�P�P�P���ڂ̕��ɋL�O�i�����������邱�Ƃ��v�悵�܂����B�L�O�i�́A�_�Ɗ��Z�p�������̖��O���������s�V���c�ƃy���V���ł��B�u���F�_�ƂƊ��v�̉�ʂ̉E���ɃA�N�Z�X�ԍ����̂��Ă��܂��̂ŁA�����ɁA�u
�O�P�P�P�P�P�P
�v�̐������\�����ꂽ���́A�ȉ��̂Ƃ���ɂ��̉�ʂ̕��ʂ������肭�������B�L�O�i�������肵�܂��B���킹�āA�����ŔN�S�s���Ă���u�_���j���[�X�v���������炨���肵�܂��B
�@
| ���ʑ��t�� |
�F |
�_�Ɗ��Z�p�������@��撲�����@�������Ȓ��@����r�� |
| �@ |
�@ |
��305-8604�@��錧���Ύs�ω���3-1-3 |
| �@ |
�@ |
�@TEL�F 029-838-8180�@FAX�F029-838-8199 |
| �@ |
�@ |
�@e-mail: imagawa@affrc.go.jp |
�@
�@
�{�̏Љ�@�P�O�P�F�_�ƋZ�p��n�����l�����A�����q�F��
�Ƃ̌������@�i�P�X�X�W�jISBN4-259-51747-3
�@ |
�@
�@���̖{�́A�����U�N�S������P�O�N�R���܂ł̂S�N�ԁA�u�_�Ƌ��ϐV���v�ɏ���������ꂽ�u���{�́u�_�v�����l�����v�����q�ɂ��ď����ꂽ���̂ł���B���҂́A���a�R�P�N�ɔ_�яȂɓ��Ȃ��A�l���_�Ǝ�����A��B�_�Ǝ�����A�M�є_�ƌ����Z���^�[�ȂǂŐ���E�e���T�C�Ȃǂ̌����ɏ]�������o��������A���̌�A�_�ѐ��Y�Z�p��c�����ǂŐU���ے��A��Ȍ����Ǘ����A�ǒ��Ȃnj����Ǘ����C�����o�������镝�̍L���������҂ł���B
�@
�@�����ƒn���͑��݂ɋ����e����^���Đi�����Ă����B������u���i���v�ƌĂ�ł���B�S�U���N�̒n���̗��j�́A�\�w�̒n�����ω��Ɛ����j�̎��������ڂɊ֘A���邱�Ƃ������Ă���B���҂͂��̌��ۂ�_�Ƃɂ����������������ɁA�l�̖��ɏœ_�ĂĂ���B
�@
�@�_�Ƃ̗��j�����ǂ��Ă݂�ƁA����̗���ɂ�����炸���̐ߖڐߖڂŋZ�p�������ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă��������킩��B����ƋZ�p�͋��i�����Ă���̂ł���B�����A���̋Z�p��n�����̂͐l�ł���B����ɂ�������炸�A���̋Z�p��n�����l�͈ӊO�ɒm���Ă��Ȃ��B���҂����M���v���������̂́A�Z�p��n�����l�����́u��v�Ɓu�z���v�𑽂��̐l�ɏЉ������������ł���B
�@
�@���҂̔_���Ȃł̐����������������炩�A�e���炩�肩�łȂ����A���e�͐���A���앨�E���A�ʎ��E��E�Ԃ��A�_�Ƌ@�B�E�{�݁A�{�Y�E�{�\�ɂ킯�������Z���ēǂ݂₷���B�ȉ��Ɏ������悤�ɖڎ�������߂ĊȌ�����̓I�Ȃ̂ŁA�ڎ������������ő����̂��Ƃ��z���ł���B�Ƃ͂����A�w�����ēǂ܂�邱�Ƃɔ@�i���j���͖����B
�@
�@���̏��ɂ́A����ꂪ���ɂ��A�ڂɂ������Ƃ̂���L�[���[�h���S�}���Ƃ���B�H�i����j���A�����I�E��l�H��z�E����܍��A�R�V�q�J���E�����E���d�E�ۉ��ܒ��c��E�u�����_�E�m�[�����P�O�E����P�O�O���E��\���I�E�ӂ��E����E�T�N�����{�����сE�n�N�����E�E���~�o�G�E���E�^�R���o�C���E���m�p���E�\�̃n�C�u���b�h�E���Y�ӕʋZ�p�E�l�H�����Z�p�ȂǂȂǁB
�@
�@�_�Ɗ��Z�p�������Ɗ֘A������߂Đ[���b���ӂ��Љ��B��P�b�F�Ȋw�_�@�̑�ꍆ�A�����I���J���|���䎞�h�|�B���䎞�h�̊��|�ɂ�邷�炵���ѕM�̊|�����A�_�Ɗ��Z�p�������̗��������ɂ���B���̂��Ƃ́A�u���F�_�ƂƊ� No.20�v�ŏЉ���B��V�b�F���d�ɂ��������O�A�����̔_�w�ҁ|�g�����s�|�B�g�����s�̌����̏�M�͌��Q��������ɂ܂ŋy��ł���B���a�R�O�N��ɂ͊e�n�̃_�����܂��A�␅�Q�Ȃǂɂ��_���ЊQ�̒������s���Ă���B���a�S�Q�N�ɋ���o�ϑ�w�̊w���ɂȂ�ƁA�_�ʐ쐅�n�̃J�h�~�E�����Q��Nj����A�C�^�C�C�^�C�a�̌����ɂ��]�����Ă���B
�@�ڎ��͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@
������
�y��P�b�z�Ȋw�_�@�̑�P���A�����I���J��
�y��Q�b�z��l�H��z�̐�삯�ƂȂ��������҂Ɣ_������
�y��R�b�z�i��Â���E�S�Â���̖��l
�y��S�b�z��̐_�l���������~���̑�i��u����܍��v
�y��T�b�z���y�R����ɐ��܂ꂽ��Ղ̕i��u�R�V�q�J���v
�y��U�b�z�k�C���ẴC���[�W����ς������u�����R�X�V�v
�y��V�b�z���d�ɂ��������O�A�����̔_�w��
�y��W�b�z�G���Ƃ̒����킢�ɂ����Ē������҂���
�y��X�b�z�������̒��������C���`�a�����\�@�̈�Ă̐e
�y��10�b�z���{�̈��n�}�������������ۉ��ܒ��c��̔���
�y��11�b�z�_�Ƃ̔M�C�ɔR���Đ������c���J��
�y��12�b�z���Y��������[�h�����u�u�����_���v
�@
�����앨�E��
�y��13�b�z���E��ς��������m�[�����E�e���̐��݂̐e
�y��14�b�z�H�Ɠ��̉��l�A�T�c�}�C���u����P�O�O���v
�y��15�b�z�����ɃW���K�C��������z������r�Ȑl
�y��16�b�z�e���T�C�̑����ɍv�������y�[�p�[�|�b�g�ڐA
�y��17�b�z���{�̒��̍�������߂��_������
�@
���ʎ��E��E�Ԃ�
�y��18�b�z���ݗ��߂��琶�܂ꂽ�u��\���I�v�i�V
�y��19�b�z�u���������͓G���v�̎���ɐ��܂ꂽ�����S�u�ӂ��v
�y��20�b�z�����S�̉��l����Ă��_�Ƃ���
�y��21�b�z��ɐ����A�O�ꂵ���Z�p�v�V�Łu����v���琬
�y��22�b�z�C�l���c�a�����������̎�Ȃ��f���E�G�A
�y��23�b�z���R���ˑނ����T�N�����{�u�����сv
�y��24�b�z���Q�����_�Ƃ̋~����u�{���v�C���J��
�y��25�b�z�_���Ƒ����������u�썂�v�E��
�y��26�b�z�_�Ƃ̍H�v���琶�܂ꂽ��̐ڂ��؍͔|
�y��27�b�z�o�C�I��ؑ�P���u�n�N�����v��n��
�y��28�b�z�o�C�I�̐�삯�A�E�C���X�t���[�_�Ƃ�z�����l����
�y��29�b�z�A���Ŋ��t�A�E���~�o�G�̍���ɐs�������l����
�y��30�b�z�m�����������̉Ԃɂ������Ԃ̈��Ƃ���
�@
���_�Ƌ@�B�E�{��
�y��31�b�z�_�Ƌ@�B���̈�ԑŎҁA�E���@���������l����
�y��32�b�z�S�H���Ɣ_�Ƃ��������k����@
�y��33�b�z�c�A�@�a���̑O��A�Ƒn�̉����Ă��l����
�y��34�b�z�V�_�w�҂̍Ŋ��̖��ɉ�������c�c�A�@�̔���
�y��35�b�z�_�Ƃ��I���������E�^�R���o�C���̓�
�y��36�b�z�_�����l���A�ŐV�Z�p���������ꂽ�u���m�p���v
�@
���{�Y�E�{�\
�y��37�b�z�\�Ő��E���̃n�C�u���b�h�i����琬
�y��38�b�z���E�𐧂����q�i�{�̎��Y�ӕʋZ�p
�y��39�b�z���{�Y��]���������������t�̐l�H�����Z�p
�y��40�b�z���E������������p�ʂ��l�H�D�P���̒a��
�@
�@
�{�̏Љ�@�P�O�Q�F�_�ƋZ�p��n�����l���� II�A�����q�F��
�Ƃ̌�����@�i�Q�O�O�R�jISBN4-259-51787-2
�@ |
�@
�@�u�{�̏Љ�P�O�P�v�̑��҂ł���B���҂��u�͂��߂Ɂv�Ō��M���v�����ȉ��ɏЉ��B�u�_�ƋZ�p��n�����l�����v�̑��Ղ����ǂ闷�͂��̂����B���Ղ����ǂ��Ă���ƁA�ނ�̑z�����`���A�����܂ŕ������Ă���悤�ȋC�����āA������܂ŔM���Ȃ��Ă���B��l�����̑��Ղ����ǂ��Ă���ƁA�ނ炪�����ɔ_�ƂƔ_�Ƃ������A�t�ɔ_�Ƃɂ����Ɍh������Ă��邩��m�邱�Ƃ��ł��āA�S���܂�v��������B�ƁB
�@
�@�O�҂͂Q�X�S�łɂS�O�b���f�ڂ���Ă������A���̕҂́A�R�U�W�łɂR�V�b���f�ڂ���Ă���B���̐�������A���ꂼ��̘b�ւ̎v�����ꂪ�A�O�҂��Z���Ȃ��Ă��邱�Ƃ����ĂƂ��B�Ƃ��ɖڎ��ɂ���悤�ɁA�u���n���̔_�ƌ����v�Ɋ|���钘�҂̎v���͔M���B
�@
�@��P�b�̓c���F�j�A��Q�b�̕��H��l�A��R�b�̍��X�ؒ��~�E�����Y�ł́A���ꂼ��呺�v���Y�A�p���������A��X�L�˂ȂǗ��j�I�ɂ悭�m��ꂽ���ۂƂ̗��݂����ꂨ�����낢�B��P�b�̓c���F�j�ŁA�i�n�ɑ��Y�̍�i�́u�Ԑ_�v�Ɉًc��������Ƃ���Ȃǂ́A���҂̔M���v����������Ă���悤�ŁA�܂��Ɉ����ł���B���̂ق��A���ؐԕF��{���Ȃǒ����ȂЂƂтƂ��o�ꂵ�A���҂̋��{�̐[�����_�Ԍ�����B
�@
�@�c��Ȏ����̎��W�͂��邱�ƂȂ���A���̖{�ɂ͓��l�⌻��̎ʐ^�����������ʂ��ɂ��킵�Ă���B���ꂪ�A�����̑z�����������Ă��D�̍ޗ��ɂȂ��Ă���B���̏�A����ɑ����^�Ԓ��҂̎p�́A����������_�w�Ȃ����̐��ɂȂ����Ƃ��̂����Ɍ���Ă���B
�@
�@���̖{�ł́A�����Ă���̐l���o�ꂷ��B��\�I�Ȑl�́A��P�V�b�ɓo�ꂷ��T�c�}�C���u�R�K�l�Z���K���v���[���c��퉮�u��䌒�g�v�ł���B��䌒�g�́A�_�Ɗ��Z�p�������̏��㏊���ł���ƂƂ��ɁA�����́u�F�̉�v�̉�ł�����B��P�V�b�͂��Гǂ�łق����B�Ē��ƃT�c�}�C��������Ȃ��������T�c�}�C����̍�䌳�����̎p���A����������Č����ɏ�����Ă���B
�@
�@�܂��Љ�������Ƃ͎R�قǂ��邪�A�Љ�ڂ����Ȃ�Ɣ���s���ɂ��e������̂ŁA���̂�����ŏI���B�ڎ��͈ȉ��̒ʂ�ł���B
�@
�����n���̔_�ƌ���
�y��P�b�z�����J���̉Ԃ��炩�����u�_�̉Ԑ_�v
�y��Q�b�z���|�̋Z�_�Ƃ���ꂽ�{�݉��|�����̑�����
�y��R�b�z���{�̗{�\�Z�p���m�������e�q�����[
�@
�����c��
�y��S�b�z���[�̈�琢�I�̑�i��ɁA�u�T�̔��v�̔���
�y��T�b�z�ߑ�i��̐�삯�u���H�P�R�Q���v�A�A�̈琬��
�y��U�b�z���Q����~�����u����_�тP���v�ƈ琬�҂̉h��
�y��V�b�z�u����S�Ձv���琶�܂ꂽ����̑�i��u���{���v
�y��W�b�z���^�̂��������āu�T�T�j�V�L�v
�y��X�b�z�n��u�����h�Ă̐��u���������܂��v
�y��10�b�z��Q�������Ă��ꂽ�ϗ�E�ǐH���i��u�ЂƂ߂ڂ�v
�y��11�b�z������͔|�ƃe���T�C�͔|�ɓq������M
�@
������E���n
�y��12�b�z�����̑剡�j�u�_�тU�P���v����Ă��ώ@��
�y��13�b�z�Y�E���̎x���Ő��܂ꂽ���ǂ�p�i��u�`�z�N�R���M�v
�y��14�b�z���E�ō������̃r�[�����u�͂�ȓ���v
�y��15�b�z�z�����疼��ɁA�s���̑哤�i��u�G�����C�v
�y��16�b�z��w�����������T�c�}�C���̏����u�g�ԁv
�y��17�b�z�T�c�}�C���u�R�K�l�Z���K���v���[���c���
�y��18�b�z�s�{�����_�̑���������\�ɂ����u�ʔN�T�C���[�W�����v
�@
���ʎ��E��E�Ԃ�
�y��19�b�z�u�e���v�u�V���v�Ȃǂ��琬�����i�V�̐_�l
�y��20�b�z�⏕�i�킩��s���o�̑�i��Ɉ�����i�V�u�K���v
�y��21�b�z����̃J�L�u�x�L�v��S���ɕ��y
�y��22�b�z�䕗�������炵���J�L�́u���������v
�y��23�b�z�_�Ƃ̑n���͂����肠�����v�\�R�́u�Ί_�C�`�S�v
�y��24�b�z�N���X�}�X�ɊԂɍ����C�`�S�́u����v
�y��25�b�z�X�[�p�[����̊��n�g�}�g�u�����Y�v
�y��26�b�z�����E�h����{��ɂ����������͔|
�y��27�b�z�ፑ�Ƀ`���[���b�v������z������r�Ȑl��
�y��28�b�z���E�ɂ͂����A�t�F�j�b�N�X�A�o���
�@
���a�Q���h��
�y��29�b�z�u�E���J�͊C��n��v�C�O����̔�����
�y��30�b�z�V�����҂��݂������ɂ₳�����_��
�@
���@�B�E�{��
�y��31�b�z�k�C���Ɉ������Â������u���������d��v
�y��32�b�z�_���̕��i����ς��������^�ʕ������@
�y��33�b�z�܂������Ȑl����������������p�c�A�@
�y��34�b�z���_�Ƃ̓����Q�s�������������h���t�@��
�y��35�b�z�~�J���_�Ƃ��d�J���������������m���[��
�@
���C�O�_��
�y��36�b�z��p���{����I�����ӕĂ�ꂽ�u�H䰕āv�̕�
�y��37�b�z����A�W�A�S��ɕ��y��������u�}�X���v
�@
�@
�����̏Љ�FJapan-Korea Cooperative Research on
Sustainability and Environmental Benefits of Paddy Farming
National Institute for Agro-Environmental Sciences, Japan and
National Institute of Agricultural Science and Technology, Korea
�@ |
�@
�@�_�Ɗ��Z�p�������́A���؋��������v���W�F�N�g�u���c�_�Ƃ̎������E���v�I�@�\�̉𖾂Ɗ����a�^�͔|�Ǘ��Z�p�̊J���v�̐��ʂ����\�����B���̃v���W�F�N�g�́A�P�X�X�V�N�T���P�T���t���̓��{����\�O���͑��Y�_�ѐ��Y�Z�p��c�����ǒ��Ɗ؍�����\����������Ǘ��ǒ��̊o���i�l�n�t�j�ɂ��J�n���ꂽ�B
�@
�@���{���́A�_�Ɗ��Z�p�����������S�ƂȂ��ăv���W�F�N�g���J�n���ꂽ�B����̒n���I�K�͂̐H���E�����̉����A�n�d�b�c�̔_�Ɗ�����̌����ɍۂ��Đ��c�_�Ƃ̓����ɂ��č��ۓI�����̊g���ړI�Ƃ������̃v���W�F�N�g�́A�����ۑ�̒������̂R�_�ɐݒ肵���B�P�j���c�_�Ƃɂ����镨���z�Ɋւ��錤���A�Q�j���c�_�Ƃɂ����鉷�g���K�X�̔�������Ɋւ��錤���A�R�j���c�_�Ƃ̌��v�I�@�\�Ɋւ��錤���B
�@
�@���̎����́u�͂��߂Ɂv�Ɓu�ڎ��v�͈ȉ��̒ʂ�ł���B�S�̂�����́A�����̒n���������̗с@�z���i�d�b�F029-838-8200�j�ɂ��₢���킹���������B
�@
�@
Human activities are closely related to the changes in the Earth's environment. The cycle of materials on a global scale has been transformed as the results of the destruction of forests for increasing the arable land area, expansion of the livestock industry, and change in the chemical composition of the atmosphere by combustion of fossil fuels, discharge of wastes, cutting through mountains for mining deposits and distribution of heavy metals on the Earth. Thus, mankind is now modifying the original environment of the Earth. The biosphere of the Earth is suffering from environmental disruption including global warming, depletion of the ozone layer, deforestation, marine pollution, air pollution, acid rain, water pollution, soil erosion, pollution with metals, reduction of biological diversity, pollution through nuclear wastes, pollution through livestock and human wastes and depletion of underground water.
�@
We have also reached environmental limits in the agriculture, forestry and fisheries industries. Productivity in a large number of existing farmlands has been reduced though new arable lands cannot be found easily. Deforestation, overgrazing, excessive fishing, salinization of soils and desertification have recently reduced the production of food. Water resources in many regions have been depleted and contaminated. Agricultural production and urban water resources will be strictly limited in the future.
�@
Agricultural activities themselves, through the increase of food production, affect the environment. Nitrous oxide derived from the application of nitrogen fertilizers and from livestock wastes and methane produced from paddy fields and ruminant livestock affect the atmosphere and cause global warming and destruction of the ozone layer.
�@
On the other hand, living things have an effect called the environment forming effect. Although their ambient environment affects living things, they, in turn, affect and create a unique environment.
�@
In areas in which agriculture and forestry are practiced, the effects of the atmosphere, soil, water, plants and animals create such a unique environment. These effects become environment preservations when they work in a positive direction for nature and human beings. This is how we define environmental preservation multi-functions of agricultural ecosystems in this paper.
�@
However, the beneficial effect of agriculture on the environment should not be overlooked. The Committee for Agriculture of the OECD suggested that agriculture is a major custodian of the environment and is endowed with multi-functions to conserve the environment. Sustainable agriculture is proposed as one way to solve the conflicting problems.
�@
How can we maintain and increase food production and control the above load on the environment?
�@ |
Katsuyuki Minami
Director General,
National Institute for
Agro-Environmental Sciences, Japan |
| �@ |
�@ |
�@ |
Ki-Cheol Eom
Deputy Director General,
National Institute of Agricultural
Sciences and Technology, Korea |
�@
�@
�@
1. Material Cycling in Rice Paddy fields
�@1) Material Dynamics in Rice Paddy Soils
�@�@�@�@(1)�@Flow Model of Nutrients and Water in Paddy Soils
�@2) Energy Benefit in Rice Paddy Fields
�@�@�@�@(1)�@Utilization of Coated Fertilizers for Low Input Farming Systems
�@3) Changes of Bio-Diversity in Rice Paddy Ecosystems for Long-Term Farming
�@�@�@�@(1)�@Assessment of Bio-Diversity in Paddy Farming System
�@
2. Mitigation of Greenhouse Gases from Rice Paddy Fields
�@1) Emission of Greenhouse Gases from Rice Paddy Fields
�@�@�@�@(1)�@Monitoring of Greenhouse Gases Emissions from Agricultural Field
�@2) Mitigation Technics of Greenhouse Gases on Cultivation Management
�@�@�@�@(1)�@Improvement of Organic Matter and Fertilizer Technics for Mitigation of Greenhouse Gases
�@3) Improvement of Cropping System for Effective Reduction of Greenhouse Gas Emission
�@�@�@�@(1)�@Effect of the Difference in Cultivation Method on Greenhouse Gas Emission
�@
3. Assessment of Environmental Effects of Paddy Farming
�@1) Quantitative Assessment of Beneficial Effects of Paddy Farming
�@�@�@�@(1)�@Technical assessment of Paddy Farming for Land and Environmental Conservation
�@�@�@�@(2)�@Social and Economic Evaluation of the Multifunctional Roles of Paddy Farming
�@2) Quantitative Assessment of Environmental Loads from Paddy Farming
�@�@�@�@(1)�@Quantitative Assessment of Environmental Loads from Paddy Fields
�@
�@
��`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o�Ɋւ���
���B�c��Ɨ�����̎w��2001/18/EC��
����II��⑫����������
�@ |
�@
�@���B�ψ���́A2002�N�V��24���A��`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o�Ɋւ��鉢�B�c��Ɨ�����̎w��2001/18/EC�̕���II��⑫�����������𐧒肷�錈����s�����B
�@
�@���B�c��Ɨ�����ɂ����2001�N3��12���ɍ̑����ꂽ�w��2001/18/EC�́A����܂ł̗�����w��90/220/EC�ɂ����A���B�ɂ������`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o�ɂ��Ă̊�{�@�߂��߂����̂ł���B
�@
�@�V�w�߂́A�p�[�g�`�i�����j�A�p�[�g�a�i��s�ȊO�̖ړI�ł�GMO�̈Ӑ}�I���o�j�A�p�[�g�b�i���i�Ƃ��Ă̂��邢�͐��i����GMO�̏�s�j�A�p�[�g�c�i�ŏI�����j����\�������{���ƁA����I�`�i��Q��(2)�Ō��y���ꂽ�Z�p�j�A����I�a�i��R���Ō��y���ꂽ�Z�p�j�A����II�i�����X�N�]���̌����j�A����III�i�͂��o�ɕK�v�ȏ��j�A����III�`(�����A���ȊO�̈�`�q���ϐ����̕��o�Ɋւ���͂��o�ɕK�v�ȏ��j�A����III�a�i��`�q���ύ����A���i���q�A���Ɣ�q�A���j�̕��o�Ɋւ���͂��o�ɕK�v�ȏ��j�A����IV�i�lj����j�A����V�i�قȂ�菇�̓K�p�Ɋւ���K���j�A����VI�i�]�����̃K�C�h���C���j�A����VII�i���j�^�����O�v��j�A����VIII�i���w�߂Ƃ̑Ή��\�j����Ȃ��Ă���B
�@
�@���̎�������́A�V�w�߂̕���II��⑫���āA�����X�N�]���̖ړI�A�v�f�A��ʓI�����ƕ��@���A���ڍׂɏq�ׂ������ł���B
�@
�@�����ł́A���B����Ɍf�ځiOJ L 200, 2002�N7��30��, 22�y�[�W�j���ꂽ�A��������𐧒肷��ψ����F
���A���{��ɉ��Ď����B���e���K�ɕ\������Ă��Ȃ�����������Ǝv����̂ŁA�����Ŋm�F���Ă������������B
�@
�@��������̊e�͂̌��o���͈ȉ��̂Ƃ���ł���F
�@
���� L 200�A30/07/2002�A22-33�y�[�W
�@
��`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o����ї�����w��90/220/EEC�̔p�~�Ɋւ��鉢�B�c��Ɨ�����̎w��2001/18/EC�̕���II��⑫�����������iguidance notes�j���߂�2002�N7��24���̈ψ����
�i�����ԍ� C(2002) 2715�j
�i���B�����iEEA�j�Ɋւ��镶���j
(2002/623/EC) |
�@
���B�����̈ψ���́A
�@
���B�����̐ݗ����ɗ��ӂ��A
�@
��`�q���ϐ����̊��ւ̈Ӑ}�I���o����ї�����w��90/220/EEC�i�P�j�̔p�~�Ɋւ���2001�N3��12���̉��B�c��Ɨ�����̎w��2001/18/EC���P�A���ɕ���II�̑�P�p���O���t�ɗ��ӂ��A
�@
�ȉ��̂��ƂɊӂ݁F
�@
�i�P�j�w��2001/18/EC�Ɋ�Â��A�������A�܂��K�v�ɉ����Ĉψ���́A��`�q���ϐ���(genetically modified organism)�i�ȉ���GMO�j���Q ���瑼�̐����ւ̈�`�q�̈ړ��ɂ���āA���ړI���邢�͊ԐړI�ɋN���邩������Ȃ��l�̌��N�Ɗ��ւ̐��ݓI�L�Q�e��(potential adverse effects)���A���̎w�߂̕���II�ɏ]���āA�ʎ���Ɋ�Â��Đ��m�ɕ]������邱�Ƃ�ۏ��Ȃ���Ȃ��A
�i�Q�j�w��2001/18/EC�̑�U��(2)(b)�Ƒ�13��(2)(b)�Ɋ�Â��AGMO�̕��o���邢�͏�s(placing on the market)���Q �̓͂��o���Q �ɂ́A�����X�N�]�����Q �ƁA���̎w�߂̕���II�ɏ]���āAGMO�̕��o���邢�͏�s�̋N���肤����e���ɂ��Ă̌��_���܂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A
�i�R�j�w��2001/18/EC�̕���II�́A�����X�N�]���̖ړI�A�v�f�A��ʓI�����A����ѕ��@�Ɋւ��ďڍׂȎ�������ɂ���ĕ⑫���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A
�i�S�j���̌���Œ�߂�[�u�́A�w��2001/18/EC�̑�30��(1)�Ɋ�Â��Đݒu�����ψ���̈ӌ��ɏ]���A
�@
�ȉ��̂Ƃ��肱�̌�����̑������F
�@
�@
���̌���̕����Ŏ�����������́A�w��2001/18/EC�̕���II�̕⑫�Ƃ��Ďg�p����B
�@
�@
���̌���́A�����e���ɑ��B�����B
�@
2002�N7��24���A�u�����b�Z���ɂ����č̑��B
�@ |
���B�ψ���
Margot WALLSTRÖM
�ψ���ψ� |
�@
�i�P�j OJ L 106�A17.4.2001�A1�y�[�W�B
���Q�@���̎�������Ŏg�p�����A��`�q���ϐ����A�Ӑ}�I���o�A��s�A�����X�N�]���Ȃǂ̗p��́A�w��2001/18/EC�̑�Q���ʼn��L�̂悤�ɒ�`����Ă���B
�u�����v�Ƃ́A���ȑ��B�A�܂��͈�`�����̓`�B���\�Ȃ��ׂĂ̐����̂������B
�u��`�q���ϐ����v�Ƃ́A��z����с^�܂��͎��R�̑g�݊����ł͖{���N����Ȃ����@�ň�`���������ς��ꂽ�A�l�Ԃ���������������
�u�Ӑ}�I���o�v�Ƃ́A��ʂ̏Z���Ɗ��Ƃ̐ڐG�𐧌����A��ʂ̏Z���Ɗ��ɑ��č������S����^���邽�߂̓��ʂȕ������ߎ�i���g�p�����ɁAGMO�܂���GMO�̑g�����������ɈӐ}�I�ɓ������邱�Ƃ�����
�u��s�v�Ƃ́A�Ή����������ɂ�邩�ɂ�����炸�A��O�҂�����\�ɂ��邱�Ƃ������B
�u�͂��o�v�Ƃ́A�{�w�߂ŗv�����Ă�������������̏��Ǔ��ǂɒ�o���邱�Ƃ�����
�u�\���ҁv�Ƃ́A�͂��o���o����҂�����
�u���i�v�Ƃ́AGMO�܂���GMO�̑g��������Ȃ�A���邢�͊ܗL���钲�����ł���A��s�������̂�����
�u�����X�N�]���v�Ƃ́A���ړI���ԐړI���A�܂������I���x���I���ɂ�����炸�AGMO�̈Ӑ}�I���o�܂��͏�s�������N������������Ȃ��l�̌��N����ɑ��郊�X�N�̕]���ł���A����II�ɏ]���čs������̂�����
�@
�w��2001/18/EC�̕���II�Ō��y����Ă�������X�N�]���̖ړI�A
�\���v�f�A��ʓI�����A����ѕ��@�_�Ɋւ��������� |
�@
�@�����X�N�]���iERA�j�Ƃ́A�w��2001/18/EC�̑�Q��(8)�ŁA�u���ړI���ԐړI���A�܂������I���x���I���ɂ�����炸�AGMO�̈Ӑ}�I���o�܂��͏�s�������N������������Ȃ��l�̌��N����ɑ��郊�X�N�̕]���v�ƒ�`����Ă���B���̎w�߂̉��ł̈�ʓI�`���̈�Ƃ��āA��S��(3)�́A�������A�K�v�ȏꍇ�ɂ͈ψ���ɁA���ړI�A�ԐړI�ɋN���邩������Ȃ��l�̌��N�Ɗ��ւ̐��ݓI�L�Q�e�����A���������Ǝ�e���̐����ɉ����Ċ��e�����l�����āA�ʎ���Ɋ�Â��Đ��m�ɕ]������邱�Ƃ�ۏ��邱�Ƃ����߂Ă���BERA�́A���̎w�߂̕���II�ɏ]���Đ��s����A�܂��p�[�g�a�A�b�ł����y����Ă���B����II�́A���������Ǝ�e���̐����ɉ����Đl�̌��N�Ɗ��ւ̉e�����l�����A�B�����ׂ��ړI�A�������ׂ��v�f�AERA�����s���邽�߂ɏ]���ׂ���ʓI�����ƕ��@����ʓI�Ȍ��t�ŏq�ׂĂ���B
�@
�@�\���҂́A��U��(2)�ɏ]���ĈӐ}�I���o�̂��߂ɁA���邢�͑�13��(2)�ɏ]���ď�s�̂��߂ɁAERA���܂ޓ͂��o���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�\���҂��x�����A�w��2001/18/EC�ɏ]���ĕ�I�œK��ERA�̏��Ǔ��ǂɂ�鎷�s��e�Ղɂ��A�����Ĉ�ʎs���ɓ�����ERA�v���Z�X����邽�߂ɁA���̎�������́A�w��2001/18/EC�ւ̕���II��⑫���AERA�ɂ��Ă̕��@�͂������ړI�A�������T������B
�@
�@ERA�̂U�̒i�K���4.2�͂ɏq�ׂĂ���B
�@
�@
�@�w��2001/18/EC�ւ̕���II�ɂ��ƁAERA�̖ړI�́AGMO�̈Ӑ}�I���o�A���邢�͏�s�������Ă��邩������Ȃ��l�̌��N�Ɗ��Ɋւ���A���ړI���邢�͊ԐړI�A�܂������I���邢�͒x���I��GMO�̐��ݓI�L�Q�e�����ʎ���Ɋ�Â��Ċm�F���A�]�����邱�Ƃɂ���BERA�́A���X�N�Ǘ����s���K�v�����邩�ǂ������m�F���A���邢�͎g�p���ׂ������Ƃ��K�ȕ��@�����߂�ړI�Ŏ��{���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@���̂��߁A�w��2001/18/EC�Ō��y�����悤�ɁAERA�͈Ӑ}�I���o�i�p�[�g�a�j�Ə�s�i�p�[�g�b�j��ΏۂƂ���B���ɕp�ɂ̏�s���K�����������ւ̈Ӑ}�I���o���܂ނƂ͌���Ȃ����A�s��ł͈Ӑ}�I�ȓ�������ɑ��݂���i���Ƃ��A�H�i�A��������щ��H�i�̎g�p�݂̂�GMO���܂ށA�܂��͍\������_�Y���j�B�����̏ꍇ���AERA��͂��o�̎葱���Ɋ܂߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�����̃f�[�^�A���Ԃ̎ړx��ʐϓI�ȈႢ�ɂ���āA��ʓI�ɈӐ}�I���o�̂��߂�ERA�Ə�s�̂��߂�ERA�̊Ԃɂ͈Ⴂ�����邾�낤�B
�@
�@����ɁA�����̎�������́A�������A�A���A����ѓ����ȂǁA���ׂĂ�GMO��ΏۂƂ���B����܂ł̂Ƃ���A�Ӑ}�I�ɕ��o����A���邢�͏�s���ꂽGMO�̑啔���͍����A���ł��邪�A����͕ς�邾�낤�B
�@
�@ERA�́A���X�N�Ǘ��̕K�v�����m�F���邽�߂̊�b�Ƃ��āi�K�v�ȏꍇ�͎g�p���ׂ������Ƃ��K�ȕ��@�Łj�A�܂��œ_���߂����j�^�����O�����{���邽�߂̊�b�Ƃ��Ė𗧂i��R�͎Q�Ɓj�B
�@
�@�ʓI�ȕ]���̑S�̂Ƃ��ẮA���YGMO�iGMO�ʂ̕]���j��GMO�����o������e���i���Ƃ��A�T�C�g�ʂ̕]���A�����\�ł���A�n��ʂ̕]���j��Ώۂɂ���B
�@
�@��`�q���ς̏����̔��W�ɂ���āA�Z�p�̐i���ɑ��ĕ���II�Ǝ��������K�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�ł��낤�B�P�זE�����A���⍩���Ȃǂ̂��܂��܂�GMO�^�C�v�A���邢�̓��N�`���̊J���̂悤��GMO�̓��ʂȎg�p�̂��߂ɁA���v��������ɋ敪���邱�Ƃ́A���B�����̂ɂ����āA���ʂ�GMO�̕��o�ɂ��Ă̓͂��o�ɂ��o�����\���ɂȂ�Ή\�ł��낤�i����III�̑�S�p���O���t�Ɩ{��������̑�U�́j�B
�@
�@�R�������ϐ��}�[�J�[��`�q�̎g�p�Ɋւ��郊�X�N�]���͔��ɖ��m�Ȗ��ł���A���̌��Ɋւ�������������Ɋ�������邾�낤�B
�@
�@�w��2001/18/EC�̕���II�ɐl�̌��N�A�܂��͊��Ɋւ���GMO�̂��܂��܂ȁu�e���敪�v���L�q���Ă���B���ʂɗ������邽�߂ɁA�w�߂̒��̈ȉ��̗p��̒�`�́A���̂悤�ɐ�������Ă���F
�@
�| �u���ړI�e���v�Ƃ́A�l�̌��N�܂��͊��ւ̈ꎟ�I�e�����w���A���̉e����GMO���̂̌��ʂł���A�܂����ۂ̈��ʘA����ʂ��Đ�������̂ł͂Ȃ��i���Ƃ��A�W�I�����ւ�Bt�őf�̒��ړI�e����l�̌��N�ւ�GM�������̕a�����̉e���j�A
�@
�| �u�ԐړI�e���v�Ƃ́A���ۂ̈��ʘA����ʂ��āA���̐����Ƃ̑��݉e���A������`�����̈ړ��A���邢�́A�g�p���܂��͊Ǘ����̕ω��Ƃ������@������Đ�����A�l�Ԃ̌��N�܂��͊��ւ̉e�����w���G �ԐړI�e���̊ώ@�̌��ɂ߂��x��₷���i���Ƃ��A�W�I�����̌̐��̌��������̍����̌̐��ɉe�����y�ڂ��ꍇ�A���邢�́A�����̒�R����S�g���̌��ʂ̔��B�������̑��ݍ�p�̕]����K�v�Ƃ���ꍇ�G ����ǂ��A�_��g�p�̍팸�̂悤�Ȃ������̊ԐړI�e���́A�������Ɍ���邾�낤�j�A
�@
�| �u�����I�e���v�Ƃ́AGMO�̕��o���Ԓ��Ɋώ@�����l�̌��N����ւ̉e���������B�����I�e���́A���ړI�ł�����A�ԐړI�ł����肤��i���Ƃ��A�Q����R����t��������`�q���ϐA����ېH���鍩���̎��S���邢�͓����GMO�ւ̖\�I�ɂ�銴�̍����l�̃A�����M�[�̗U���j�A
�@
�| �u�x���I�e���v�Ƃ́AGMO�̕��o�̊��Ԓ��ɂ͊ώ@����Ȃ��Ă��A���o�̌����I����ɒ��ړI�܂��͊ԐړI�Ɍ����l�̌��N�܂��͊��ւ̉e���������i���Ƃ��A�Ӑ}�I�ȕ��o���琔�����Ɍ����GMO�̒蒅��N���s���́A��`�q���ώ��Ȃǂ̂悤��GMO�������Ԑ������Ă���ꍇ�͔��ɏd�v�ł���G ���邢�͈�`�q���ύ앨�Ƌ߉���Ƃ̌��G�킪���R���Ԍn�ŐN���I�ɂȂ�ꍇ�j�B
�@
�@�Ƃ��ɒx���I�e���������I�ɂ̂����ꍇ�A���̉e�����m�肷��͍̂���낤�B���j�^�����O�i���L�Q�Ɓj�̂悤�ȓK�ȑ[�u�́A�����̉e�������o����̂ɖ𗧂B
�@
�@
�@�\�h�����ɏ]���AERA�́A�ȉ��̂悤�Ȉ�ʓI�����Ɋ�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�@
�| �L�Q�ȉe������\���̂���GMO�̓��肳�ꂽ�`���Ƃ��̗��p�́A����N���������A�����̗��p�����̔���ϐ����ɂ���Ď����ꂽ���̂Ɣ�r���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�����Ɛ����ԑ��ݍ�p����сA�����̊��m�̕ψقȂǁA��e���̃x�[�X���C���́A�m�F���ꂤ��GMO�̂�����i�L�Q�ȁj�`�������O�Ɋm�肵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̃x�[�X���C���́A�����̕ω��Ɣ�r���邱�Ƃ��ł����_�Ƃ��Ė𗧂B���Ƃ��A�h�{�ɐB�앨�̏ꍇ�́A�`���]�����C�������o�����߂Ɏg�p�����e�앨���r���͂̒��ɓ���Ȃ����Ȃ��B�L���ɐB�앨�̏ꍇ�́A�K�ȓ�����`�q�n����Ώۍ앨�ɓ����B�앨���߂���z�ɂ���ĊJ�����ꂽ�ꍇ�A�����������e�X�g�͂����Ƃ��K�ȑΏƂ�p���A���̐e�앨�̎����ƒP���ɔ�r���Ȃ����Ƃ��d�v�ł���B
�@
�����̃f�[�^���\���łȂ��ꍇ�A�x�[�X���C���͔�r���邽�߂̑��̊���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�x�[�X���C���́A�����I�v�f�Ɣ��I�v�f�i���Ƃ��A���R�ی쐶���n�A�_�n�A���邢�͉����n�j�A���邢�́A���܂��܂Ȋ��̑g�����ȂǁA��e���ɂ��Ȃ荶�E����邾�낤�B
�@
�| ERA�́A���p�\�ȉȊw�I�A�Z�p�I�ȃf�[�^�Ɋ�Â��A�Ȋw�I�Ɍ�肪�Ȃ�����₷�����@�ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
���ݓI�L�Q�e���̕]���́A�Ȋw�I�A�Z�p�I�f�[�^�ƁA�֘A�f�[�^�̓���A���W����є��f�̂��߂̋��ʂ̕��@�Ɋ�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�f�[�^�A����A����уe�X�g�́A���m�ɋL�q���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɁA�Ȋw�I�ɐM���������郂�f�����O��@�̗��p�́AERA�ɗL�p�ȁA��������Ă���f�[�^��^���邾�낤�B
�@
ERA�́A���낢��ȃ��x���ŕs�m�������l�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�Ȋw�I�ȕs�m�����́A�Ȋw�I��@�̂T�̓�������ʏ�A������F �I������ϐ��A�g�p���鑪��@�A�̎悷��T���v���A�g�p���郂�f������э̗p������ʊW�B�Ȋw�I�s�m�����͊����f�[�^�Ɋւ���_����W����f�[�^�s�����琶���邱�Ƃ�����B�s�m�����͕��͂̎��I�A�ʓI�v�f�ɊW�����邩������Ȃ��B�s�m�����̃��x���̓x�[�X���C���ɂ��Ă̒m����f�[�^�̃��x���f���邽�߁A�\���҂͌��݂̊��s�̉Ȋw�I�s�m�����Ɣ�r���āA���̕s�m�������x�������K�v������i�f�[�^�̌����A�m���M���b�v�A�W�����A���G���Ȃǂ̕s�m���̕]���j�B
�@
ERA�̓f�[�^���s�����邽�߁A�����������ׂĂ̎���ɖ��m�ɂ͓������Ȃ���������Ȃ��B�Ƃ��ɁA�N���邩������Ȃ������I�ȉe���ɂ��ẮA�f�[�^�̓���\�������ɒႢ��������Ȃ��B���̏ꍇ�A�l�̌��N����ъ��ւ̗L�Q�e����h�~���邽�߂ɗ\�h�����ɏ]���āA�Ƃ��ɓK�ȃ��X�N�Ǘ��i�ی��i�j���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
��ʓI�����Ƃ��āAERA�́A�͂�����Ǝ����ŗ��t����ꂽ��r������o���̑��ɁAGMO�̈Ӑ}�I���o�A���邢�͏�s�ɔ����N���肤�郊�X�N�ւ̓K�Ȓ����̌��ʂ�g�ݓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�i�������ߗ��p�V�X�e���ł̎����Ɏn�܂�A�Ӑ}�I���o�����s�܂ł̂��ׂĂ̒i�K�ɂ��āj�i�K�I���g�݂̗��p���L���Ȃ��Ƃ�����B�e�i�K�œ�����f�[�^�͎葱���̊��Ԓ��ɁA�ł��邾�������ɏW�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������߃V�X�e���ɂ�����͋[�I�������́A�Ӑ}�I���o�Ɋ֘A���̂��錋�ʂ�^���邱�Ƃ��ł��邾�낤�i���Ƃ��A�������̔����͔������Ԍn�̒��ŃV�~�����[�V�������邱�Ƃ��\�ł���A�܂��͐A���̔����͂�����x�A�����̒��ŃV�~�����[�V�������邱�Ƃ��ł���j�B
�@
��s�����GMO�ɂƂ��āAGMO��������ɋ߂���Ԃ́A�Ӑ}�I���o����̊֘A��������A���p�\�ȃf�[�^�ɂȂ�͂��ł���B
�@
�| ERA�́A�ʎ���Ɋ�Â��čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́A�Ƃ�킯GMO�����łɊ����ɂ��邱�Ƃ��l������ƁA���YGMO�̃^�C�v�A�g�p�ړI�A�\���̂����e���ɂ���āA�K�v�ȏ��͕ς�邩������Ȃ��Ƃ������Ƃł���B
�@
���܂��܂Ȑ����iGMO���Ɓj����i�T�C�g���ƁA�����Ēn�悲�Ɓj�̌X�̓����͕����L�����߂ɁAERA�̓P�[�X�o�C�P�[�X�i�ʎ��Ⴒ�Ɓj�̌����ōs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��`�q���ϔ������i���ׂł���A���ݍ�p���悭�𖾂���Ă��Ȃ��j�A��`�q���ϐA���i�H���⎔���Ɏg�p����鍂���A���A���邢�͎����̒������Ȃǁj�A����ш�`�q���ϓ����i�������A��Q������������ݔ\�͂̍��������G ���邢�́A���ݓI�ȕ��z�悪�L���������Ȃǁj�́A���e���ɂ����đ傫�ȕψق�����B
�@
����ɁA�l�����ׂ����̓����i����ȃT�C�g�A����Ȓn��j�͍L���ψٕ�������B�P�[�X�o�C�P�[�X�]���𗠕t���邽�߂ɁAGMO�ɂ�������e���̏��f�������n�̒n��f�[�^�ނ��邱�Ƃ����ɗ����낤�i���Ƃ��A���B�̂��܂��܂Ȕ_�Ƃ⎩�R�̐����n�ɂ�����GMO�A���̖쐫�߉���̐���Ɋւ���A���w�I�f�[�^�j�B
�@
�\���҂́A�_��g�p�̂悤�ɁA����GMO���J��Ԃ��ĕ��o���邱�ƂȂǁA�ߋ��ɈӐ}�I�ɕ��o������A���邢�͏�s���ꂽ�Ǝv����֘A���邷�ׂĂ�GMO�ƐV����GMO�Ƃ̊ԂɁA�L�Q�ȑ��ݍ�p�����邩������Ȃ����Ƃ��l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���܂̕��o�Ɣ�r���āA�J��Ԃ��ɂ����o�́A�����ɏ펞�A���݂���悤�ɂȂ邽�߂ɁA���̂���GMO�̌o��Z�x�������Ȃ錴���ɂȂ邩������Ȃ��B
�@
GMO�Ɛl�̌��N�܂��͊��ւ̉e���Ɋւ���V���������\�ɂȂ����ꍇ�́AERA�͈ȉ��̂��߂ɍēx�A���{���邱�Ƃ��K�v�ɂȂ邩������Ȃ��F
�@
�| ���X�N���ς�����ǂ��������肷��A
�| ���X�N�Ǘ�������ɉ����ĉ�������K�v������ǂ��������肷��B
�@
�V���ȏ����ꂽ�ꍇ�A�������ɑ[�u����K�v�����邩�ǂ����ɂ�����炸�AGMO�̕��o���邢�͏�s�̔F���Ԃ�ύX������A���邢�̓��X�N�Ǘ��[�u������K�v����]�����邽�߂̐V����ERA���s��Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�i��U�͂��Q�Ɓj�B�V���ȏ��́A������j�^�����O�v�悩��A���邢�́A���̑��̊֘A����o�����瓾����\��������B
�@
ERA�ƃ��j�^�����O�́A���ڂɘA�����Ă���BERA�͐l�̌��N�Ɗ��ւ̗L�Q�e���ɏœ_�����Ă����j�^�����O�v��̂��߂̊�b�ƂȂ�BGMO�̈Ӑ}�I���o�i����III�̊֘A�����ɑΉ�����p�[�g�a�j��GMO�̏�s�i����VII�ɑΉ�����p�[�g�b�j�̂��߂̃��j�^�����O�v��̗v���͈قȂ�B�����I�ȊĎ����܂ރp�[�g�b�̃��j�^�����O�́AGMO�̒����I�ɋN���邩������Ȃ��L�Q�e���ɂ��Ẵf�[�^������ŁA�d�v�Ȗ������ʂ������낤�B���j�^�����O�̌��ʂ�ERA���m�F���A���邢��ERA�����������ƂɂȂ�B
�@
�| ERA�̈�ʓI�����ɂ́A���o�Ə�s�ɂ��Ắu�ݐϓI�����e���v�̉�͂��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�����B�ݐϓI�����e���Ƃ́A���A�����A�y��엀�x�A�y�뒆�̗L�@���̗A����/�H���A���A�������l���A�ƒ{�q���ƍR�������ɊW����ϐ����ȂǁA�l�̌��N�Ɗ��ɑ��Ēm���Ă���~�ϓI�e���������B
�@
���ݓI�ȗݐϓI�����e�����������邽�߁AERA�͎��̂悤�Ȗ����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�@
�| GMO�Ǝ�e���Ƃ̒����I�ȑ��ݍ�p�A
�| �����I�ɏd�v�ƂȂ�GMO�̌`���A
�| �Ӑ}�I���o�̌J��Ԃ��A�܂��́A�����Ԃɂ킽���s�A
�| �ߋ��ɈӐ}�I�ɕ��o���邢�͏�s���ꂽGMO�B
�@
�Ƃ��ɒ����I�e���A�i���Ƃ��A�����̏����ܑϐ��j�ɂ��Ă̏����ɕK�v�ł���A�܂����j�^�����O�v��͗ݐϓI�����e����]�����邽�߂̏d�v�ȃf�[�^����邱�Ƃ��\�ł���A�ꕔ���͘g�g�݂̒��ŁA�\���ɒ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̍��ڂɊւ��邳��Ȃ��������������邾�낤�B
�@
�@
�@
�@ERA�́A���̌`���ɂ��Ċ֘A����Z�p�I�A�Ȋw�I�ȍזڂ��l���ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�@
�| ��`�q���ς̎�e�����A���Ȃ킿�e�����A
�| ��`�����̑g�ݍ��݁A���邢�͏����ɂ���`�q���ρA�x�N�^�[�ƃh�i�[�i���^�����j�Ɋ֘A������A
�| GMO�A
�| �Ӑ}������o���邢�͎g�p�Ƃ��̋K�́A
�| ���ݓI��e���A������
�| �����̊Ԃ̑��ݍ�p�B
�@
�@�ގ��̐�����ގ��`�����������̕��o�ƁA�ގ��̊��Ƃ̂����̑��ݍ�p�̏��́AERA�ɖ𗧂B
�@
�@�w�߂̕���IIIA��IIIB�Ŏ��������iGMO�A�h�i�[�A��e�����A�x�N�^�[�A���o�Ɗ��̏�ԁAGMO�Ɗ��Ƃ̑��ݍ�p�����GMO���j�^�����O�Ɋւ�����j�Ȃǂ̓͂��o�́A���̎w�߂̃p�[�g�a�ɏ]����GMO�̈Ӑ}�I���o�̑O�ɁA���邢�͎w�߂̃p�[�g�b���ɏ]���ď�s�̑O�ɁA�ŏ��ɕ��o�܂��͏�s���s���������̏��Ǔ��ǂɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�����\�����ނɂ́A�w�߂̑�U��(2)�Ƒ�13��(�Q)�ɏ]���Ċ��S��ERA�A���Ȃ킿ERA�̏d�v���ɉ����āA���ׂĂ̓_�𗧏��邽�߂ɕK�v�ȏڍׂȂ��̂��܂ސ��I�ȊW��ނ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�\���҂́A���p��������A�g�p�������@�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�w�߂̕���IIIA��IIIB�ŗv���������Ɋ�Â����A��e�����A�h�i�[�A�x�N�^�[�A��`�q���ς���т���GMO�Ɋւ�����́AGMO�������I�ɕ��o�A���邢�͏�s������������ɉe������Ȃ��B���̏��́AGMO�̉\���̂���L�Q�Ȃ��ׂĂ̌`���i���ݓI�n�U�[�h�Fpotential hazards�j���m�F�����b�ɂȂ�B�����GMO�A���邢�͓��ނ�GMO�̕��o�ɂ����ē�����m���ƌo���́A���̕��o�̐��ݓI�n�U�[�h�Ɋւ���d�v�ȏ���^����B
�@
�@�w�߂̕���IIIA��IIIB�ŋ��߂��Ă���悤�ɁA�Ӑ}�I���o�A��e������т����̊Ԃ̑��ݍ�p�Ɋւ�����́AGMO�����o��������̊��ƁA���̕��o�̋K�͂��܂ޏ����ƊW������B���̏��́AGMO�̂���������ƗL�Q��������Ȃ����ׂĂ̌`���̒��x�����肷��B
�@
�@
�@�w��2001/18/EC�̑�S�A�U�A�V����ё�13���Ō��y����ERA�ɂ��Ă̌��_�������o���ꍇ�AERA�ɂ������Ȏ菇�Ƃ��Ĉȉ��̓_�Ɏ��g�ނׂ��ł���B
�@
�@�u�n�U�[�h�v�i�L�Q�Ȍ`���j�́A�l�̌��N�A����с^�܂��͊��ɊQ���邢�͗L�Q�e���������N�������鐶���̐��ݐ��ƒ�`����B
�u���X�N�v�Ƃ́A�n�U�[�h�̌��ʂ̏�Ԃ̓����ƁA���̃n�U�[�h��������\���̒��x�ilikelihood�j�Ƃ̑g�����ł���B
�@
4.2.1. ��P�i�K�F �L�Q�ȉe���������N������������Ȃ��`���̊m�F
�@
�@�l�Ԃ̌��N���邢�͊��ɗL�Q�ȉe���������炷�\���������`�q���ςɊW�̂���GMO�̂��ׂĂ̌`�����m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̕��o�◘�p�̏������ł�GMO�Ɣ�GMO�̌`���̔�r�́AGMO�̈�`�q���ς��琶�������̐��ݓI�L�Q�e�����m�F���邱�Ƃ𑣐i���邾�낤�B�N���肻���ɂ��Ȃ����Ƃ𗝗R�ɁA�N���肤��L�Q�e�����y�����Ȃ����Ƃ��d�v�ł���B
�@
�@GMO�̐��ݓI�L�Q�e���́A���Ⴒ�ƂɈقȂ�A�ȉ��̂��Ƃ��܂܂�邾�낤�F
�@
�| �A�����M�[����Ő��̉e���ȂǁA�l�̕a�C�A
�| �Ő��e���A�ꍇ�ɂ���ăA�����M�[���̉e���ȂǁA�����ƐA���̕a�C
�| ��e�����̌̌Q�̓��ԂƊe�̌Q�̈�`�I���l���ւ̉e��
�| �����ǂ̓`�����������A���邢�͐V���ȕa������x�N�^�[�̌����ƂȂ�a���ۂ̊��̕ω��A
�| ���Ƃ��A�l��ƒ{�̎��ÂɎg�p�����R�������ɑϐ�������`�q�̓����ɂ���āA�l�̗\�h�Ǝ��Â�ƒ{�̎��ÁA���邢�͐A���h�u���u�̏�Q�ɂȂ邱��
�| �����n�����w�i�����n�����w�I�z�j�A�Ƃ��ɓy�뒆�̗L�@���̕����̕ω��ɂ��Y�f�ƒ��f�̏z�ւ̉e���B
�@
�@��L�̐��ݓI�L�Q�e���̗�́A�w��2001/18/EC�̕���IIIA��IIIB�ŏq�ׂ��Ă���B
�@
�@�L�Q�ȉe���������N������������Ȃ��啔���̊m�F�\�ȃn�U�[�h�i�L�Q�Ȍ`���j�́AGMO�̒��ɈӐ}�I�ɓ������ꂽ�֘A��`�q���`�q�Q�A�����Ă����̈�`�q���甭�����Ă���^���p�N���ƊW�����邾�낤�B�V���ȗL�Q�e���i���Ƃ��A���ʓI���ʁj���A������`�q���쐬���邽�߂Ɏg�p�������@�̌��ʂ�A������`�q���}�����ꂽGMO�Q�m���̔z��ʒu�̌��ʂƂ��āA����邱�Ƃ�����B�����̓�����`�q����e�����ɓ]�ʂ���ꍇ�A�܂��́A��̓�����`�q��GMO�ɓ]�ʂ���ꍇ�́A���܂��܂ȓ�����`�q�̐��ݓI���ݍ�p���A����������ƌ㐬�I��p���邢�͒��ߓI��p�����邩������Ȃ����Ƃ��l���ɓ���āA�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�ł��邾�����m�Ƀn�U�[�h���߂邱�Ƃ��d�v�ł��邪�A�����̏ꍇ�A���Ɏ������ڂɏ]���ăn�U�[�h���������A���̎��ɁAERA�̖ړI�̂��߂Ɋm�F���ׂ��ʂ̃n�U�[�h���߂邱�Ƃ��L���ł���i���Ƃ��Γ��ʂȎ���Ől�̌��N�ɐ��ݓI�L�Q�e�����m�F���ꂽ�ꍇ�A�A�����Q�����Ɠőf�Y�����́AERA�ł͕����Č������Ȃ���Ȃ�Ȃ��j�B
�@
�@�n�U�[�h��GMO�̒��ɑ��݂���Ƃ���ƁA����͏�ɑ��݂��邱�Ƃ������̎����Ƃ݂Ȃ����Ƃ��ł���B�����̃n�U�[�h�́A���̌��ʂ̏�Ԃ�����\���̒��x�Łi��R�i�K�j���������邱�Ƃ�����A�܂������̌��ʂ̏�Ԃ̊K�������X�ɈقȂ邱�Ƃ����肦��i��Q�i�K�j�B���ǁA�X�̃n�U�[�h�́A����GMO�ɂ��ėv��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�������AERA�̂��̒i�K�ł́A�L�Q�ȉe�����邩������Ȃ���`�q���ς̌��ʁA�����炳���n�U�[�h���������邱�Ƃ݂̂��K�v�ł���B��P�i�K�ł́AERA�̈ȍ~�̒i�K�̉Ȋw�I������^����B���̒i�K�ł������A�X�̐��ݓI�n�U�[�h�ɂ��āA�㔼�̒i�K�ōl�����邱�Ƃ��ł���悤�ɁA�Ȋw�I�s�m�����̌ʐ������m�F���邱�Ƃ��d�v�ł���B
�@
�@�L�Q�ȉe���́A�@����ʂ��Ē��ځA�N���邱�ƁA���邢�͊ԐړI�ɋN���邱�Ƃ�����A�����ɂ͎��̂��Ƃ��܂܂��ł��낤�F
�@
�| ���̒���GMO�̊g��
�@
���z�o�H�́AGMO�̕��z�̉\���̂���o�H�������A���Ȃ킿���̒��ւ́A���邢�͊��̒��ł́A���ݓI�n�U�[�h�̐��ݓI�o�H�������Ă���i���Ƃ��ΐl�Ԃւ̓Ő��F �L�łȔ������A�܂��́A�L�łȃ^���p�N���̋z���j�B
�@
GMO�������ɍL����\���́A���Ƃ��A�ȉ��̂��Ƃɍ��E����邾�낤�F
�@
�| GMO�̐����w�I�K���x�i���R���̒��ŋ����͂����߂�`���̔�����A�����g���̎��I�A�ʓI�ȉ��ςɂ���āA�L���Ȋ��̒��Ŕ\�͂����߂邽�߂ɐv���ꂽGMO�A���邢�͕a�C�⏋���A�����A�����̂悤�Ȕ��I�X�g���X�̂悤�Ȏ��R�̑I�����ɑ��đϐ�������GMO��������ɂ�����R���������Y�j
�| �Ӑ}�I���o�܂��͏�s�̏����i�Ƃ��ɁA���o�̖ʐςƋK�́A���Ȃ킿�A���o�����GMO�̐��j�A
�| �Ӑ}�I���o�܂��͏�s�̉\���A�܂��́A���ւ̔�Ӑ}�I���o�̉\���i���Ƃ��Ή��H�p��GMO�j�A
�| �����\�ȗv�f�i���Ƃ��Ύ�q�A��E�A���̑��j�̕��A���A�����Ȃǂɂ�镪�U�o�H�A
�| ���ʂȊ��̌����i����ꏊ�A�܂��́A����n��j�F �ꏊ�ʁA�n��ʂɕ]�����邽�߂ɂ́AGMO�ɊW�����e���̏��f�������n�ʂ̃f�[�^�ނ��邱�Ƃ��𗧂��낤�i���Ƃ��A���B�̂��܂��܂Ȕ_�Ƃ⎩�R�̐����n�ɂ����āAGMO�A���ƌ��G�\�ȋ߉��쐶��̐����Ɋւ���A���f�[�^�j�B
�@
�X��GMO�̐������Ԃ�]�����邱�Ƃ��d�v�ł���A���Ȃ킿������GMO�̓���̐��́A��ʂɐ����c��₷���B�܂�GMO�͂��܂��܂Ȑ����n�ɎU�z�����\��������A�蒅���₷���Ȃ鏀�����ireadiness�j��]�����邱�Ƃ��d�v�ł���B���Ƃ��A���L�̂��Ƃ��܂߂āA�ɐB�A�����A�x���^�ɂ��Č������K�v�ł��낤�F
�@
�| �A���ɂ��āF �ԕ��A��q�Ɖh�{�̂̐����\�́A
�| �������ɂ��āF �����`�ԂƂ��Ẳ�E�̐������A���邢�͐����Ă��邪�A�|�{�s�\�ȏ�Ԃ̔������̐��ݐ��B
�@
�S�̂Ɋg�傷����ݐ��́A��A��`�q���ρA��e���i���Ƃ������ł̐A���͔|��C�ł̋��{�B�j�ȂǂɈˑ����A���Ȃ�ω����邾�낤�B
�@
�| ���̐����ւ̓�����`�`���̓`�B�A���邢�͓��ꐶ���ň�`�q�I�ɉ��ς��ꂽ���ۂ�
�@
����n�U�[�h�́A��������ŁA�܂��́A���̎�ւ̈�`�q�̈ړ���ʂ��ėL�Q�ȉe�����邩������Ȃ��i�����I���邢�͐����I�Ȉ�`�q�̈ړ��j�B���̐����i���������̏ꍇ�A�ʏ�͑��Ǝ\�Ȑ����j�ւ̈�`�q�̈ړ��̑��x�ƒ��x�́A���Ƃ��A���̂��Ƃɍ��E�����ł��낤�F
�@
�| ���ς��ꂽ��`�q�z����͂��߂Ƃ���GMO���̂̔ɐB����
�| ���o�̏����ƋC��i���Ƃ��A���j�̂悤�Ȍʂ̊��v��
�| ���B�����w��̈Ⴂ�A
�| �_�ƍs�ׁA
�| ���G�̉\���̂��鑊��̗L�����A
�| �ړ��Ǝ����x�N�^�[�i���Ƃ��A�����Ⓓ�A��ʂ̓����j�A
�| �����ɑ����e�����̗L�����B
�@
��`�q�̈ړ��ɂ�����̗L�Q�e���̔����p�x�́A���o�����GMO�̐��Ɗ֘A�����肤��B��`�q�g�����A���̑傫�ȕޏ�́A�䗦����l���Ă��A�����ȕޏꂩ��̈�`�q�̈ړ��Ƃ͑S���قȂ邱�Ƃ����邾�낤�B����ɁA���G�̉\�������鑊��A���A���邢�́A��e�A���̑��݂Ɋւ��鎿�I�A�ʓI���i�e�����鋗�����ɑ��݂���A���ɂ��āj�����ɏd�v�ł���B
�@
�����A���Ɠ����ɂ��ẮA�����A�߉���A�����ɂ������A����і��W�Ȏ�ւ̈�`�q�̈ړ��̉\���Ɋւ��āA��ʂ�����ɕK�v�ł���B
�@
�������̏ꍇ�́A�����I�Ȉ�`�q�̈ړ����A���������d�v�Ȗ������ʂ����B�����`�`���́A���Ƃ��A�v���X�~�h��o�N�e���I�t�@�[�W����Ė��ڂɊW���鐶���Ƃ̊Ԃŗe�ՂɈړ����邱�Ƃ����肦��B�������̍������ݑ��B���������Ȑ����Ɣ�r���āA��r�I���������ň�`�q�̈ړ����\�ɂ��Ă���B
�@
������`�q�̈ړ��ɂ����GMO�̍����W�c�������A���炭���āA���܂��܂Ȉ�`�q�ƐA���̑g�������ł��邱�Ƃɂ��A�����ł͂Ƃ��ɒ����̗L�Q�e���̕��G�ȃp�^�[�����������Ƃ����肤��B���̃p�^�[���́A��葽���̈�`�������W�c�̒��Ɉړ�����قǁA��蕡�G�ɂȂ邾�낤�i���Ƃ��A��`�q�̐ςݏd�ˁj�B
�@
�������̎���ł́A��`�q���ς̕��@����`�q�̈ړ��̉\����ς��邱�Ƃ����肤��i���Ƃ��A��g�ݍ��݃v���X�~�h�A���邢�̓E�C���X�̃x�N�^�[�̏ꍇ�j�B��`�q���ς̕��@����`�q�̈ړ��̉\�������������邱�Ƃ����肤��i���Ƃ��A�t�Α̌`���]���j�B
�@
��`�q�̈ړ��́A���R�W�c�̒��̓�����`�`���̎c���ɋA�����邾�낤�B����GMO�Ɉ�`�q�̈ړ��̉\��������Ƃ��Ă��A���ꂪ�{�������Ă��郊�X�N�A���Ȃ킿�����A�蒅���A���邢�͗L�Q�ȉe���������N�����\�͂̕ω���K�������Ӗ����Ȃ��B����́A������`�����A������A����ѐ��ݓI��e�������܂ގ�e���ɍ��E����邾�낤�B
�@
�| �\���^�̕s���萫�ƈ�`�I�ȕs���萫
�@
��`�I���萫���邢�͕s���萫���A�\���^�̈��萫���邢�͕s���萫�������炵�A�n�U�[�h�ƂȂ���x���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��`�q���ς̕s���萫�ɂ���āA����ꍇ�́A�쐶�^�C�v�̕\���^�ւ̋t�ˑR�ψق��N�������Ƃ����肤��B���̂悤�ȑ��̏ꍇ���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�@
�| �����̓�����`�q���܂܂��`���]���A�����C���ɂ����āA���̌�̕����ߒ��ŁA���ɓ�����`�q�������ƁA������`�q�̏��Ȃ��V���ȕ\���^�̐A���ɂȂ邱�Ƃ�����ꍇ�A
�| ��œˑR�ψّ̂��s���萫�ɋN�����āi����̓ˑR�ψق��N�������߁j�A�Ő�������ꍇ�A
�| ������`�q�̕�������`�q�s�������ɂȂ���ꍇ�A
�| �R�s�[�������ɑ����ꍇ�A
�| �]�ڈ��q�̍đ}�����N����A����`���q�̑}���œ�����`�q���������邱�Ƃɂ���āA�V���ȕ\���^��������ꍇ
�| ������`�q�̔������x�����d�v�ł���ꍇ�i���Ƃ��ΗL�ŕ����̔��������ɒႢ�j�A���߈��q�̈�`�I�s���萫�ɂ���ē�����`�q�̔����������Ȃ邩������Ȃ��B
�@
�\���^�̕s���萫�́A�͔|���̊��Ƃ̑��ݍ�p���琶���邱�Ƃ�����̂ŁA������`�q�̔����ɑ�����I�A�_�ƓI�v���̉e�����AERA�Ō������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
������`�q�̔�����GMO�̓���̕����Ɍ��肳���ꍇ�i���Ƃ��A����̐A���g�D�j�A���߂̕s���萫�ɂ���ē�����`�q�������S�̂ɔ�������\��������B����Ɋ֘A���āA���߃V�O�i���i���Ƃ��A�v�����[�^�[�j�͏d�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�Ƃ���A�������K�v�ł���B
�@
�܂��A���鐶���̃��C�t�T�C�N���̓���̊��ԁA���邢�͓��ʂ̊��̏����ŁA������`�q�̔�������������K�v������B
�@
GMO���ɐB�͂������Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁA����̕s����������`�q��GMO�̒��ɓ�������邱�Ƃ�����i���Ƃ��A���铱����`�q�̈ړ��Ɗg�U��h�~���邽�߂Ɂj�B�s����������`�q�̕s���萫�́A������`�q�̓`�d���܂˂��A���̔ɐB�͂������A�L�Q�ȉe���������炷���Ƃ����肤��B
�@
���܂��܂ȓ�����`�q�̈��萫�́A�����GMO�����łȂ��A���ɂ����Ă��Ƃ��ɒ����̉e���ɂƂ��ďd�v�ł���B
�@
�| ���̐����Ƃ̑��ݍ�p�i��`����/�ԕ��̌����ȊO�j
�@
���h�{�i�K�̑��ݍ�p�̕��G�����l�����āA����GMO���܂ޑ��̐����Ƃ̑��ݍ�p�̉\�����A���Ӑ[���]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���e���������N����������Ȃ����ړI�ɗL�Q�ȑ��ݍ�p�ihazardous interaction�j�ɂ́A���̂��Ƃ��܂܂�邾�낤�F
�@
�| �l�i���Ƃ��A�_�ƎҁA����ҁj�ւ̖\�I�A
�| �ƒ{�ւ̖\�I�A
�| �y��A�ꏊ�A���A���Ȃǂ̓V�R�����Ƃ̋����A
�| ���̐����̎����W�c�̓]�ʁA
�| �L�ŕ����̑��o���A
�| ���قȂ鐬���p�^�[���B
�@
��ʂɁA��`�q���ςɂ���Đ����w�I�K���x�����܂�AGMO�́A�V���Ȋ��ɐN�����A�����̐�����ɒu�������\��������B�����̏ꍇ�A����̗L�Q�e���̔����́A���o�̋K�͂ɔ�Ⴗ��B
�@
�| �Y������ꍇ�ɂ͔_�ƍs�ׂ��͂��߂Ƃ���Ǘ��̕ύX
�@
GMO�̈Ӑ}�I�ȕ��o�̂�ނȂ����ʂƂ��āA�Ǘ����@�̕ύX�̑Ó����́A���s�̕��@�Ɋ�Â��ĕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�_��Ǘ��̕ύX�ɂ́A���Ƃ��A���̂��Ƃ��W���邩������Ȃ��F
�@
�| �앨�̔d��A�A���t���A�͔|�A���n�A�^���i���Ƃ��A�����ȕޏꂠ�邢�͑傫�ȕޏ�ɐA���t����j�A�^�C�~���O
�| �֍�i���Ƃ��A���N���邢�͂S�N���Ƃɓ���̍앨���͔|����j�A
�| �a���Q�h���i���Ƃ��A�A���p�E���܂̎�ނƎU�z�ʁA���邢�́A�ƒ{�p�R�������̎�ނƓ��^�ʁA�����Ȃ���A��֎�i�j�A
�| ��R���̊Ǘ��i���Ƃ��A�����ܑϐ��A���ɑ��鏜���܂̎�ނƎU�z�ʁA���邢��Bt�^���p�N���ɂ�鐶���I�h���̎g�p�̕ύX�A���邢�́A�E�C���X�̉e���j�A
�| �k��n�Ɨ{�B�ƃV�X�e���̊u���i���Ƃ��A�A���͔|�̊u�������A���邢�́A�{����̊u���̓����j�A
�| �_�ƍs�ׁiGMO�_�ƂƗL�@�_�@�Ȃǂ̔�GMO�_�Ɓj�A
�| ��_�ƃV�X�e���ɂ�����Ǘ��i���Ƃ��AGMO�͔|�n�悩��̎��R�����n�̊u�������j�B
�@
4.2.2. ��Q�i�K�F �L�Q�e�����������ꍇ�ɁA���ꂼ��̗L�Q�e���̐��ݓI���ʂ̏�Ԃ̕]��
�@
�@���ꂼ��̐��ݓI�L�Q�e���̌��ʂ̒��x��]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�\���̂���L�Q�Ȍ`���������\���̒��x�̑��Ɂi��4.2.3�A��R�i�K���Q�Ɓj�A���̌��ʂ̏�Ԃ̓�����]�����邱�Ƃ́A���X�N�]���̏d�v�ȕ����ł���B���̏�Ԃ̓����͈Ӑ}�I�ɕ��o����A�܂��͏�s�����GMO�̉��炩�̐��ݓI�n�U�[�h�̌��ʂ̏�Ԃ��͂�����Ɨ����ł���Ƃ������x�������B
�@
�@���̌��ʂ̏�Ԃ̓x�[�X���C���Ƃ̊W�ł݂�ׂ��ł���A�����炭�ȉ��̂��Ƃɂ���ĉe�������F
�@
�| ��`�I�\���A
�| �m�F���ꂽ�e�L�Q�e���A
�| ���o�����GMO�̐��i�K�́j�A
�| GMO�����o�������A
�| �}����i���܂ޕ��o�̏����A
�| ��L�̑g�����B
�@
�@�m�F���ꂽ�X�̗L�Q�e���ɂ��āAGMO�ɂ��炳��鑼�̐����A�W�c�A�킠�邢�͐��Ԍn�ɑ��錋�ʂ̏�Ԃ�]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����ɂ́AGMO�����o����邱�ƂɂȂ��Ă�����i�ꏊ�A�n��j�ƕ��o���@�̏ڍׂȒm�����K�v�ł���B���̌��ʂ̏�Ԃ́A�����I�Ő[���ȗL�Q�e��������ꍇ��A�����I�ɁA�i���I�ȗL�Q�e���Ȃ邩������Ȃ�������̏ꍇ�ł��A�u����������v�A����������Ɓh�������ȁh�A����сh���Ȑ���h����A�u�����v�A����������Ɓh���Ȃ�h�܂ł��܂��܂ł���B
�@
�@���̌��ʂ̏�Ԃ̓������A�ʓI�\���Ƃ��āu�����v�A�u�����x�v�A�u�Ⴂ�v���邢�́A�u����������v�Ɖ\�Ȃ�\�����ׂ��ł���B����ꍇ�͓��ʂ̊��ł͗L�Q�e�����m�F���邱�Ƃ��s�\�ł���B���̏ꍇ�ɂ́A����̗L�Q�e���Ɋ֘A���郊�X�N�́A�u����������v����������ƁA�h�������ȁh�ƁA�]�����邱�Ƃ��ł���B
�@
�@�ȉ��̂��Ƃ���ɍL���Ӗ��ʼn���I�A�萫�I�Ȏ���Ƃ��Ē�Ă���B�����͌���I�ŁA���ꂾ���Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ʂ̏�Ԃ��r�l�ʂ���Ƃ��ɍl�����Ă��悢�\���ɂ��邽�߂̂��̂ł���F
�@
�| �u�����x���̌��ʂ̏�ԁv�Ƃ́A�Z�����邢�͒����ɁA��Ŋ뜜��ƗL�v�����ȂǁA���̂P��܂��͕�����̐������Ȃ�ω����邱�Ƃ����肤��B���̂悤�ȕω��ł́A���̐��Ԍn����с^�܂��͑��̊֘A���鐶�Ԍn�̋@�\�ɕ��̉e���������炷�悤�Ȏ�̌������邢�́A���S�Ȑ�ł��܂ނ��Ƃ����邾�낤�B���̂悤�ȕω��́A�����炭�t�]���e�ՂłȂ��A�����������Ԍn�̉������炭�x�����낤�B
�@
�| �u�����x�̌��ʂ̏�ԁv�Ƃ́A���̐����̌̌Q���x�ɂ��Ȃ�ω������邩������Ȃ����A���̎�S�̂̐�ŁA���邢�͐�Ŋ뜜���L�v��ɂ����Ȃ�[���ȉe�����^����悤�ȕω��͂Ȃ����낤�B�t�]���\�ȏꍇ�ɂ́A�W�c�Ɉꎞ�I�ɁA���Ȃ�̕ω�������ꍇ���܂܂��ł��낤�B���Ԍn�̋@�\�ɐ[���ȕ��̉e�����Ȃ���A�����e��������ꍇ���܂ނ�������Ȃ��B
�@
�| �u��x���̌��ʂ̏�ԁv�Ƃ́A���̐����̌Q�̖��x�̕ω��͏������A���̐����̂����Ȃ�̌Q�������S�Ȑ�łɂ͂����炸�A���Ԍn�̋@�\�ɕ��̉e�����y�ڂ��Ȃ��B�e�����邩������Ȃ������́A�Z���Ȃ��������ɐ�ł��뜜����Ȃ���A�L�v�łȂ���݂̂ł���B
�@
�| �u���������錋�ʂ̏�ԁv�Ƃ́A�����̂����Ȃ�W�c��A�����Ȃ鐶�Ԍn�ɂ����Ă��d�v�ȕω��������N�����Ȃ����낤�B
�@
�@��L�̗�́A�W�c�ł�GMO�̐��ݓI�L�Q�e���f���Ă��邪�A�ꍇ�ɂ���ẮA�X�̐����ɉe���������Ȃ��Ƃ���������̂����K�Ȃ��Ƃ�����B�����̃n�U�[�h�������̗L�Q�e����^���邩�����ꂸ�A����ǂ��납�A�X�̗L�Q�e���̑傫�����قȂ邩������Ȃ��B�l�̌��N�ɑ��邠���̃n�U�[�h�̗L�Q�e���́A�_�Ƃ⎩�R�̐����n�ɑ���̂Ƃ́A�قȂ邩������Ȃ��B
�@
�@���ݓI���ʂ̏�Ԃ́A���ݓI�e���ƕs�m�����̃��x�����܂߁A�e�����邩������Ȃ����Ԋw�I�\���v�f�i���Ƃ��ΐ�����A�W�c�A�h�{�i�K�A���Ԍn�j�̂��ׂĂ�ΏۂƂ���悤�ȕ��@�ŗv�邱�Ƃ��ł���B
�@
4.2.3. ��R�i�K�F �m�F���ꂽ���ݓI�L�Q�e���̔����̉\���̒��x�ɂ��Ă̕]��
�@
�@�L�Q�e����������\���̒��x�܂�m����]������ۂ̎�v�ȗv�f�́AGMO����o���悤�Ƃ�����̓����ƕ��o���@�ł���B
�@
�@�n�U�[�h�̌��ʂ̏�Ԃ̓����i��4.2.2�A��Q�i�K���Q�Ɓj�̑��ɁA�L�Q�e����������\���̒��x��]�����邱�Ƃ́A���X�N��]�������ł�����̏d�v�ȕ����ł���B���̒i�K�́A�L�Q�e�������ۂɐ����邱�Ƃ��A�ǂꂭ�炢���肻�����𐄒肷�邱�Ƃł���B����ꍇ�ɂ́A�\���̒��x�ƕp�x�̗����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��Q�i�K�i�e�L�Q�e������������ꍇ�A���̐��ݓI���ʂ̏�Ԃ�]������j�Ɠ��l�ɁA�n�U�[�h���̂̑��ɁAGMO�̐��A��e���A����ѕ��o�̏������\���̒��x�m�ɂ��邽�߂ɏd�v�ł���B�C��A�n���A�y�남��ь̌Q���v�w�I�����ƁA���ݓI��e�����̓��A�����̃^�C�v�́A�d�v�Ȍ����̈ꕔ�ł���B
�@
�@���̂��߁A�����͂ɂ��ẮA�Ӑ}�I���o���s�̂��߂ɒ�o���ꂽ�����̃��X�N�Ǘ���i�͈̔͂��Đ����c�肻����GMO�̊�����]�����邱�Ƃ��K�ł���B��`�q�̈ړ������肻���ȏꍇ�́A���ꂪ�N���肻���Ȍ����A���邢�͈ړ������������Ȓ��x���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��BGMO���a�������邢�͗L�Ő��ł���ꍇ�́A�e���������Ȋ����̕W�I�����̊�����]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@����ɁA����e����������\���̒��x�́A���̃��X�N�̔�����h�~������ʂȃ��X�N�Ǘ���i�Ɉˑ����邾�낤�i���Ƃ��A�ԕ��̎U�z�͉ԏ��̏����ɂ���ĕs�\�ɂȂ�͂��ł���j�B
�@
�@�m�F���ꂽ�e�L�Q�e���ɂ��āA���̌��ʂ̏�Ԃ̑��ΓI�ȉ\���̒��x�́A�ʓI�ɕ]�����邱�Ƃ������炭�ł����A�u�����v�A�u�����x�v�A�u�Ⴂ�v���邢�́A�u����������v�Ƃ������t�ŕ\���ł���B
�@
�@��L�̗�́A�W�c�ɑ���GMO�̐��ݓI�L�Q�e���f���Ă��邪�A�ꍇ�ɂ���ẮA���ꂼ��̐����ɋy�ڂ������ȉe������������̂����K�ł��Ƃ����肤��B�����̃n�U�[�h�������̗L�Q�e���������炵�A�X�̗L�Q�e���̉\���̒��x���قȂ邩������Ȃ��B�l�̌��N�ɑ��邠���̃n�U�[�h�̗L�Q�e���ƁA�_�Ƃ⎩�R�̐����n�ɑ�����̂Ƃ͈قȂ邩������Ȃ��B
�@
�@�\���̒��x�́A���ݓI�ȉe���Ȃ�тɕs�m�����̃��x���Ɋւ�����@���܂߂āA������A�W�c�A�h�{�i�K�A���Ԍn�Ƃ������e�����邩������Ȃ����ׂĂ̐��ԓI�v�f�ɓK�p������@�ŗv�邱�Ƃ�����B
�@
4.2.4. ��S�i�K�F GMO�̊m�F���ꂽ�e�`���ɂ���Đ����郊�X�N�̐���
�@
�@�L�Q�e���������N�����\���̒��x������GMO�̊m�F���ꂽ�e�`���ɂ��l�̌��N����ւ̃��X�N�̐�����A�L�Q�e���̋N����\���̒��x�ƃ��X�N���������ꍇ�̌��ʂ̏�Ԃ̓����Ƃ��������āA�ŐV�Z�p�ŁA�ł������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@��Q�i�K�Ƒ�R�i�K�ŒB�������_�Ɋ�Â��A�L�Q�e���̃��X�N���A��P�i�K�Ŋm�F�������ꂼ��̃n�U�[�h�ɂ��ĕ]�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̏ꍇ���A�ʓI�ȕ]���͂ł������ɂȂ��B�e�n�U�[�h�ɂ��Ă̕]���́A���̂��Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��F
�@
�| ���ʂ̏�Ԃ̓����i�u�����v�A�u�����x�v�A�u�Ⴂ�v���邢�́A�u����������v�j
�| �L�Q�e���̉\���̒��x�i�u�����v�A�u�����x�v�A�u�Ⴂ�v���邢�́A�u����������v�j�A
�| ����n�U�[�h�������̗L�Q�e������ꍇ�́A���ꂼ��̗L�Q�e���̓����Ɖ\���̒��x�B
�@
�@�eGMO�́A�P�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�O�ɏq�ׂ����Ƃ��ʉ����邽�߂̂�����̑����I���݂��A���Ȃ蒍�Ӑ[���s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�L�Q�e���̍������ʂ̏�Ԃ�����������\���̒��x�ƌ������A�������X�N���疳�������郊�X�N�܂ł̂��ׂĂ͈̔͂̃��X�N�ɂȂ邱�Ƃ����肤��B���̐��т́A���̎���̏ƁA�\���҂ɂ�邠��v�f�ւ̏d�ݕt���ɍ��E����邾�낤�B�����̂��ׂẮA�o�L����ERA�ɂ͂�����Ə\���ȍ����������Ē�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�m�F���ꂽ���X�N�̑����I�ȕs�m�����́A�ł��邩���莟�̊֘A�������܂߂āA�L�q����K�v������F
�@
�| ERA�̂��܂��܂ȃ��x���ł̉���Ɛ���A
�| ���܂��܂ȉȊw�I�]���ƌ����A
�| �s�m�����A
�| �ɘa��i�̊��m�̌��E�A
�| �f�[�^���瓱�����Ƃ��ł��錋�_�B
�@
�@ERA�͗ʓI�ɕ\�킳��錋�_�Ɋ�Â��Ȃ���Ȃ�Ȃ����AERA�̌��ʂ̑����͎��I�ɂȂ炴������Ȃ����낤�B���Ƃ�����炪���I�ł���Ƃ��Ă��A�ł��邾���A���ΓI���тł���K�v������i���Ƃ��A���`�q���ϐ�����ΏƂɔ�r����j�B
�@
4.2.5. ��T�i�K�F GMO�̈Ӑ}�I�ȕ��o���s�ɂ�郊�X�N�ɑ���Ǘ��헪�̓K�p
�@
�@ERA�͂������Ǘ����邽�߂̎�i���K�v�ȃ��X�N���m�F���A���X�N�Ǘ��헪���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@���X�N�Ǘ���K�p����O�ɁA�h�~�̂��߂ɁA�Ȃ�ׂ����X�N�������ł���܂ŕ��o���@��ύX���邱�Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�L�Q�e���������N����������Ȃ��A���邢�͂͂����肵�Ȃ���`�I�v�f�́A��`�q���ς̍H���ɂ����č����T����ׂ��ł���B���ꂪ�s�\�ȏꍇ�́A�Ӑ}�I���o���邢�͏�s�̑O�ɁA�����̈�`�v�f���A��̒i�K��GMO����ł��邾���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@����ɂ��ẮA��P�i�K����S�i�K�ɂ����čl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���X�N�Ǘ��́A�m�F�������X�N�𐧌䂵�A�s�m������K�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�ی��i�́A���X�N�̃��x���ƕs�m�����̃��x���Ƃ̋ύt���Ƃ�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�֘A����f�[�^���A��̒i�K�Ŏg�p�\�ɂȂ�ꍇ�A���X�N�Ǘ����A���̐V�����f�[�^�ɏ]���ēK�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�Ǘ��ɂ���ă��X�N���팸���邽�߂ɂ́A���̎�i�́A���̖ړI�m�ɒB�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���Ƃ��A�앨�ɓ������������ɓŐ�������`�q���߉���Ɉړ����郊�X�N������ꍇ�A����̃��X�N�i���Ƃ��ΐA����j�ɖ\�I����Ȃ��ꏊ�ɂ����̋߉��킩���ԓI���邢�͎��ԓI�Ɋu�����邱�Ƃ���o�ꏊ��ύX���邱�Ƃ��K�Ȑ����i�̒��ɓ��邾�낤�B
�@
�@GMO�̎戵���Ǝg�p�̊֘A���邢����̒i�K�ł��A�u����i���Ǘ��헪�̒��ɓ���邱�Ƃ��ł���B�����ɂ́A�ɐB�̊u���A�����I���邢�͐����w�I��Q�������GMO�ɐG�ꂽ�@�B��e��̐��ȂǁA���܂��܂ȕ��@���܂ލL�͈͂Ȏ�i��g�ݓ���邱�Ƃ��\�ł���B
�@
�@�ڍׂȃ��X�N�Ǘ��菇�́A���̂��Ƃɍ��E�����ł��낤�F
�@
�| GMO�̎g�p�i�Ӑ}�I���o���s�̃^�C�v�ƋK�́j�A
�| GMO�̃^�C�v�i���Ƃ��A��`�q���ϔ������A��N���̍����A���A�����̒����A���A�������A�P��̉��ς����邢�͕����̉��ςɂ��GMO���A�P���GMO�����邢�͈قȂ��ނ�GMO���j�A
�| �����n�̒ʏ�̃^�C�v�i���Ƃ��A�����n�����w�I��ԁA�C��A����Ǝ�Ԃ̌��G����̗L�����A�N���̒��S�n�A�قȂ鐶���n�̘A���j�A
�| �_�Ɛ����n�̃^�C�v�i���Ƃ��A�_�ƁA�ыƁA���Y�{�B�A�_���n�сA�T�C�g�̑傫���A���̑���GMO�̐��j�A
�| ���R�����n�̃^�C�v�i���Ƃ��A�ی��̏�ԁj�B
�@
�@�����̂��߂ɕK�v�Ȓ����A��s�̏����ȂǒB�����ꂻ���ȃ��X�N�팸�̌��ʂ̏�ԂɊւ��郊�X�N�Ǘ��Ƃ̊֘A�̋L�q�m�ɂ��Ȃ��ꂪ�Ȃ�Ȃ��B
�@
4.2.6. ��U�i�K�F GMO�̑S�̓I�ȃ��X�N�̌���
�@
�@GMO�̑S�̓I�ȃ��X�N�̕]���́A��Ă���邷�ׂẴ��X�N�Ǘ��헪���l���ɓ���čs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@��S�i�K�A�K�v�ȏꍇ�͑�T�i�K�Ɋ�Â��āA�ŏI�I�ȕ]���́A����GMO����̗ݐϓI�e�����͂��߂Ƃ��邻�ꂼ��̗L�Q�e���ɂ�郊�X�N�̑g�����Ɋ�Â��AGMO�̗L�Q�e���̌��ʂ̏�Ԃ̓����Ƃ��̉\���̒��x���܂ށA�S�̓I�ȃ��X�N���l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̍ŏI�I�ȕ]���́A�S�̓I�ȕs�m�������܂ށA�Ӑ}�I���o���s�ɂ��S�̓I�ȃ��X�N�ɂ��Ă̗v��̌`�ŕ\����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
| �T�DGMO�̕��o���s�ɂ����ݓI�Ȋ��e���͂̌��_ |
�@
�@��R�߁A��S�߂ŊT��������ʓI�����ƕ��@�_�ɏ]���Ď��{���ꂽERA�Ɋ�Â��āA�w��2001/18/EC�̕���II�̑�D1�߂�D2�߂Ɍf����ꂽ�����Ɋւ�������AGMO�̕��o���邢�͏�s�ɂ����ݓI���e���́ipotential environmental impact�j�Ɋւ��錋�_�������o�����Ƃ��x�����邽�߂ɁA�͂��o�̒��ɓK�X�A����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
�@�Ƃ��ɔ�A���̈�ɂ����鍡��̊J���ɂ���āA�͂��o�̒��Ɋ܂߂�ׂ����ɂ��Ă̎����������ɏo�����ƂɂȂ邾�낤�B
�@
�@
�@ERA���Œ�I�Ȃ��̂Ƃ��Č���ׂ��ł͂Ȃ��BERA�́A�i�w��2001/18/EC�̑�W�����邢�͑�20���ɏ]���āj�֘A����V���ȃf�[�^���l�����邽�߂ɒ���I�Ɍ������A�X�V���A���邢�́A�����炭�ύX���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B������̌��������A�����ɂ��f�[�^�A���̈Ӑ}�I���o�ƃ��j�^�����O�f�[�^���l�����āAERA�ƃ��X�N�Ǘ��̗L�����A����������ѐ��m�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����́AERA�ɂ���Č��肳���s�m�����̃��x���ɂ����E����邾�낤�B
�@
�@���̂悤�Ȍ������̂��s������ɁAERA�ƃ��X�N�Ǘ��́A�K�X�A�K�����A���邢�̓��x�������サ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@
| 6.2. ERA�̎�����̌������ƓK�� |
�@
�@��`�q���ϋZ�p�̏����̔��W�ɂ���ĕ���II�Ǝ���������Z�p�I�Ȑi���ɓK�������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ邾�낤�B�P�זE�����A���⍩���Ȃǂ̂��܂��܂�GMO�^�C�v�A���邢�̓��N�`���̊J���̂悤��GMO�̓��ʂȎg�p�̂��߂ɁA���v��������ɋ敪���邱�Ƃ́A���B�����̂ɂ����āA���ʂ�GMO�̕��o�ɂ��Ă̓͂��o�ɂ��o�����\���ɂȂ�Ή\�ł��낤�i����III�̑�S�p���O���t�j�B
�@
�@�����GMO�̏�s�ɔ����l�̌��N�Ɗ��̈��S���Ɋ֘A����o���ƉȊw�I�؋��i��16��(2)�j�͂��Ƃ��A�w�߂̕���V�i��V��(1)�j�Œ�߂���ɏ]���āAERA�̎�����̌������Ƃ��̓K���́A�Z�p�I�Ȑi���ɓK��������K�v���ƁA�����GMO�̓���̐��Ԍn���ւ̕��o�Ɋւ��Ă̌o���i�\���ȏꍇ�j�Ɋ�Â��āA�����������ɔ��W������K�v�����A�K�v�ɉ����čl���ɓ����ׂ��ł���B

