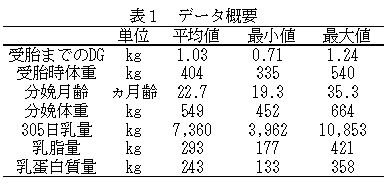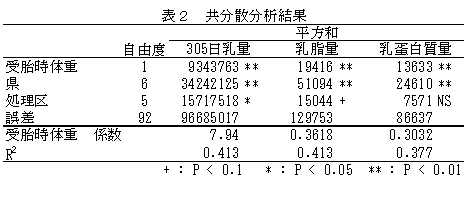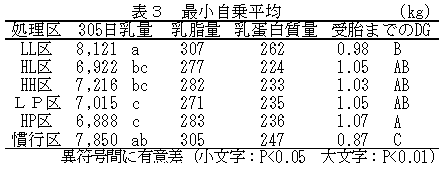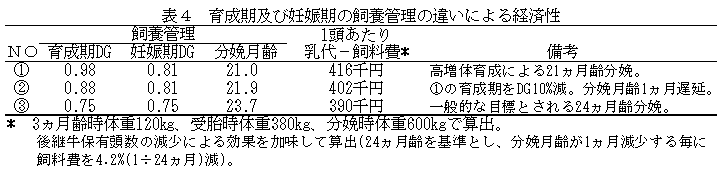初産乳生産に影響を及ぼす育成管理条件 |
|
| [要約] |
乳用育成牛の90日齢から受胎までの日増体量が1.0kgを超えると、初産乳量は低下する。一方、受胎時体重は大きいほど乳量が増加する。 |
![]()
[キーワード]乳用牛、育成牛、初産分娩月齢、乳生産性、受胎時体重 |
![]()
[担当]茨城畜セ・酪農研究室
[代表連絡先]電話:0299-43-3333
[区分]関東東海北陸農業・畜産草地(大家畜)
[分類]技術・参考 |
|
| [背景・ねらい] |
乳生産が可能となるまでに2年以上を要する育成牛の飼養管理は、飼料費、労働費等の経費に加え、施設の利用効率の点からも改善が望まれており、育成期間の短縮による初産分娩月齢の早期化が必要である。
そこで、初産種付けまでの日増体量(DG)と飼料中の粗蛋白質(CP)含量の違いが発育と乳生産性に及ぼす影響(一次試験)と、高増体育成管理における飼料中分解性(CPd)および非分解性蛋白質(CPu)含量が発育と乳生産性に及ぼす影響(二次試験)について検討し、今回それらの成績に各場所の慣行管理牛の成績を加えて、初産分娩月齢早期化を目指す飼養管理における諸要因が、初産泌乳成績に及ぼす影響を統計的に検討する。
|
![]()
[成果の内容・特徴] |
| 1. |
90日齢から体重350kgまでの間、一次試験はLL区(DG0.75kg CP14%程度)、HL区(DG1.0kg CP14%程度)、HH区(DG1.0kg CP16%程度)、二次試験はDGを0.9kgとし、体重200kgを基準として、LP区(CPd前期9.2%、後期8.3%、CPu前期4.9%、後期3.9%)、HP区(CPd前期9.5%、後期9.4%、CPu前期6.7%、後期4.9%)とする。両試験共に体重350kg到達後はDG0.75kg程度で管理する。慣行区は同時期に慣行飼養されたものとする。
|
| 2. |
一次、二次試験牛、慣行区の合計116頭の成績(表1)を用い、次の統計解析を行う。
重回帰分析(変数増減法):305日乳量、乳脂量、乳蛋白質量を目的変数とし、県、季節、生時体重、哺育期DG、受胎までのDG、受胎日齢、受胎時体重、妊娠期DG、子牛体重、分娩時体重、分娩時日齢を独立変数とする。
共分散分析:受胎時体重を補助変数とし、県、試験区を処理因子とする。 |
| 3. |
305日乳量について、重回帰分析により得られた式は、次の通りである。
305日乳量 = 3027 + (25.36 県1 -565.0 県2 -336.1 県3) +11.93 受胎時体重 (R2=0.18) 305日乳量では受胎時体重、県が変数選択され、それぞれの寄与率は8.1%、9.8%である。乳脂量では分娩時体重、妊娠期DG、県、乳蛋白質量では受胎時体重、県が選択される。
|
| 4. |
共分散分析では305日乳量において処理区間で差が認められ(表2)、LL区と慣行区は8,000kg程度で同等であるが、DG1.0kgを超えるHH区、HL区、HP区、LP区は7,000kg程度と低い(表3)。受胎までのDGはLL区程度とすべきであり、1.0kgを超えると乳量は低下する。 |
| 5. |
305日乳量は、受胎時体重(係数7.94)が大くなるほど増加する(表2)。 |
| 6. |
これらから、3ヵ月齢を120kgとし、受胎までのDGが0.98kg、分娩1週間前の体重が600kgと想定した場合、乳生産性が高い受胎時体重は380kgである。また、後継牛の保有頭数減少を考慮した「乳代−飼料費」は育成期間が短くなるほど高い(表4)。 |
|
![]()
[成果の活用面・留意点] |
| 1. |
酪農家の育成牛管理に活用できる。 |
| 2. |
要求量は日本飼養標準・乳牛1999年版に準じている。 |
| 3. |
日本飼養標準・乳牛1999年版の、育成牛の要求量には安全率が含まれている。 |
|
|
[具体的データ]
|
|
|
|
![]()
[その他] |
研究課題名:高能力乳用牛の初産分娩月齢早期化技術
予算区分:国補(先端技術)、県単
研究期間:2001〜2005年度
| 研究担当者: |
石井貴茂、関 俊雄(茨城畜セ)、川嶋賢二(千葉畜総研)、秋山 清(神奈川畜技セ)、中山博文(愛知農総試)、村上俊明(石川畜総セ)、蓮沼俊哉(富山畜試)、海内裕和(長野畜試)、寺田文典、櫛引史郎(畜産草地研) |
|
|
| 目次へ戻る |